「人が採れない」「辞めてしまう」——中小企業経営者にとって、人手不足は日々の現場で直面する最大の課題です。
2024年度には人手不足を原因とする倒産が過去最多を更新し、2030年には341万人、2040年には1,100万人の労働力が不足するという試算も出ています。
本記事では、最新の政府統計と調査データをもとに、中小企業が直面する人手不足の現状とその背景をわかりやすく整理しました。
この記事の要約
- 中小企業の65.6%が人手不足を感じており、3社中2社が影響を受けている
- 2024年度の人手不足倒産は350件と2年連続で過去最多を更新
- 生産年齢人口は1995年をピークに減少し、2025年には労働力人口が約7,170万人まで減少予測
- 業界別では建設業、運輸業、介護業、情報サービス業で人手不足が深刻
マクロ要因(人口減少・少子高齢化・労働参加率)
人口減少と少子高齢化の深刻な影響
人口動態の現状
- 総人口:2050年代に1億人を割り込む予測、約30年で人口の5分の1が減少
- 生産年齢人口:1995年をピークに減少継続、2050年には5,275万人まで減少予測
- 高齢者人口:2023年~2040年で約300万人増加予定
- 労働力人口:2024年に6,957万人と過去最高を記録するも、女性・高齢者の労働参加で維持
出典:厚生労働省「令和6年版 労働経済の分析」、総務省「労働力調査」
厚生労働省の分析によると、現在我が国は急激な人口減少に直面しており、これが労働力供給の根本的制約となっています。
特に生産年齢人口(15~64歳)の減少は顕著で、1995年の約8,716万人から2025年には約7,170万人まで減少する見込みです。
リクルートワークス研究所の将来予測によると、2030年に340万人規模、2040年に1,100万人規模の働き手不足が生じると予測されています。
労働参加率の現状と課題
| 項目 | 2024年実績 | 特徴・課題 |
| 労働力人口 | 6,011万人 | 前年比16万人の増加、女性高齢者参加で補完 |
| 就業者数 | 6,781万人 | 過去最多記録も、「人手不足」は大きな課題 |
| 女性就業率(15~64歳) | 74.1% | 就業率は改善も、雇用の質の格差が最大の課題 |
| 高齢者就業率(65歳以上) | 25.7% | OECD諸国の中でも韓国・アイスランドに次いで高い水準 |
出典:総務省統計局「労働力調査(2024年平均結果)」、厚生労働省「労働経済の分析」
地域格差と人口流出の深刻化
中小企業白書2024年版の分析では、東京圏とその他地域の所得格差と東京圏への転入超過数に一定の相関があることが判明しています。
地方から都市部への若者の人口流出が継続し、中小企業が多い地方での労働力確保がより困難になっています。
地域格差の実態
- 賃金格差:東京圏と地方の賃金差が人口移動の主要因
- 配偶者就職:配偶者の転職先確保も地方定着の阻害要因
- 中小企業集積:地方圏では中小企業が雇用の7割を支える
出典:経済産業省「2024年版中小企業白書」、内閣府「地域選択と人口移動」
ミクロ要因(給与水準・待遇・労働時間・採用力・離職率)
給与水準の課題
中小企業の賃上げ制約
2025年春闘における中小企業の賃上げ率は4.35%(経団連調査366社)と、歴史的な水準であった2024年の4.01%を上回る結果となりましたが、大企業との格差は依然として大きい状況です。中小企業は賃上げ余力が限定的であるため、深刻化する人材獲得競争において不利な立場に置かれ続けています。
| 企業規模 | 2025年賃上げ率 | 平均妥結額 | 課題 |
| 大企業 | 5.39% | 19,195円 | 比較的良好 |
| 中小企業 | 4.35% | 11,999円 | 賃上げ余力の制約 |
出典:経団連「2024年春季労使交渉結果」
労働環境と待遇の問題
労働時間の現状
- 長時間労働:中小企業ほど労働時間が長い傾向
- 2024年問題:建設業・運輸業で時間外労働上限規制により人手不足が加速
- 働き方改革の遅れ:中小企業での多様で柔軟な働き方の導入が不足
採用力・定着率の課題
中小企業は大企業と比べて採用力が脆弱で、人材獲得競争で劣勢に立たされています。
特に新卒採用市場では、知名度や待遇面で大企業に後れを取るケースが多いです。
離職率改善の成功事例
中小企業白書では、働き方改革に取り組んだ企業の成功例として、就職後3年以内の離職率を2018年の29.5%から2022年は5.4%に低下させた事例が紹介されています。定着率の改善によって計画的な人材育成が可能になり、「社員のスキル向上」につながったとしています。
人手不足が深刻な業界ランキング(2024年)
| 順位 | 業界 | 人手不足割合 | 特徴・原因 |
| 1位 | 情報サービス | 72.5% | DX需要急増、デジタル人材不足 |
| 2位 | 建設 | 70.4% | 2024年問題、高齢化、3K職場イメージ |
| 3位 | 情報サービス | 66.5% | 専門技能不足、社会インフラ需要増 |
| 4位 | 運輸・倉庫 | 66.4% | 2024年問題、EC物流需要増 |
| 5位 | リース・賃貸 | 65.9% | インバウンド需要の急回復 |
出典:帝国データバンク「人手不足に対する企業の動向調査」
経営への影響
事業制約への深刻な影響
人手不足倒産の急増
2023年の人手不足倒産は189件、2024年の人手不足倒産では342件に達し、いずれも2年連続で過去最多を更新。このうち「従業員退職型」の倒産は87件と前年の67件から大幅増加している。黒字経営でも人材不足により事業継続が困難になるケースが増加している。
| 影響領域 | 具体的な問題 | 中小企業への特殊な影響 |
| 事業運営制約 | 受注機会損失、営業時間短縮 | 少数精鋭体制での業務負荷集中 |
| 従業員負担増 | 残業時間増加、休暇取得困難 | 代替要員確保が困難、離職の連鎖 |
| 生産性低下 | 業務効率の悪化、品質問題 | DX投資余力不足、手作業依存 |
| 採用コスト増 | 求人費用増大、採用期間長期化 | 採用専門人材不足、ノウハ蓄積困難 |
まとめ
重要な視点
人手不足の解決には、短期的な人材確保策と中長期的な構造改革の両面からのアプローチが不可欠です。
企業は「人材を確保する」発想から「少ない人材で価値を創出する」発想への転換が求められています。
同時に、働く人々にとって魅力的な職場環境の構築により、持続可能な人材確保・定着を実現する必要があります。
企業レベルでの対応策
1.処遇改善と働きがい向上
- 市場競争力のある賃金水準の設定
- 柔軟な働き方精度の導入
- キャリア形成支援の充実
- 福利厚生制度の見直し・拡充
2.採用・定着率強化
- 企業ブランディングの強化
- 多様な採用チャネルの活用
- オンボーディング制度の整備
- 従業員エンゲージメント向上施策
3.業務効率化・省力化投資
- DX推進による業務プロセス改善
- AI・IoT技術の積極的導入
- 業務標準化・マニュアル化の推進
- アウトソーシングの戦略的活用
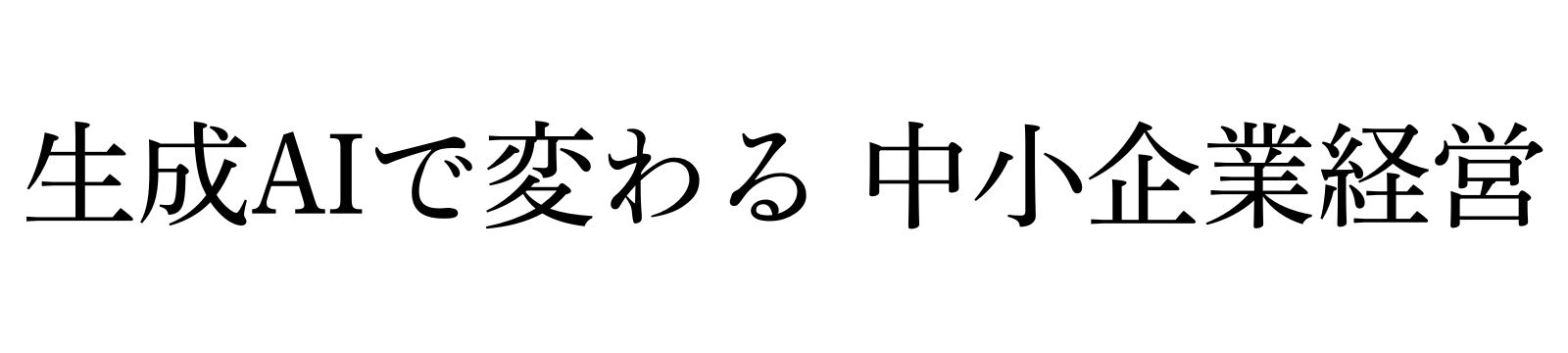
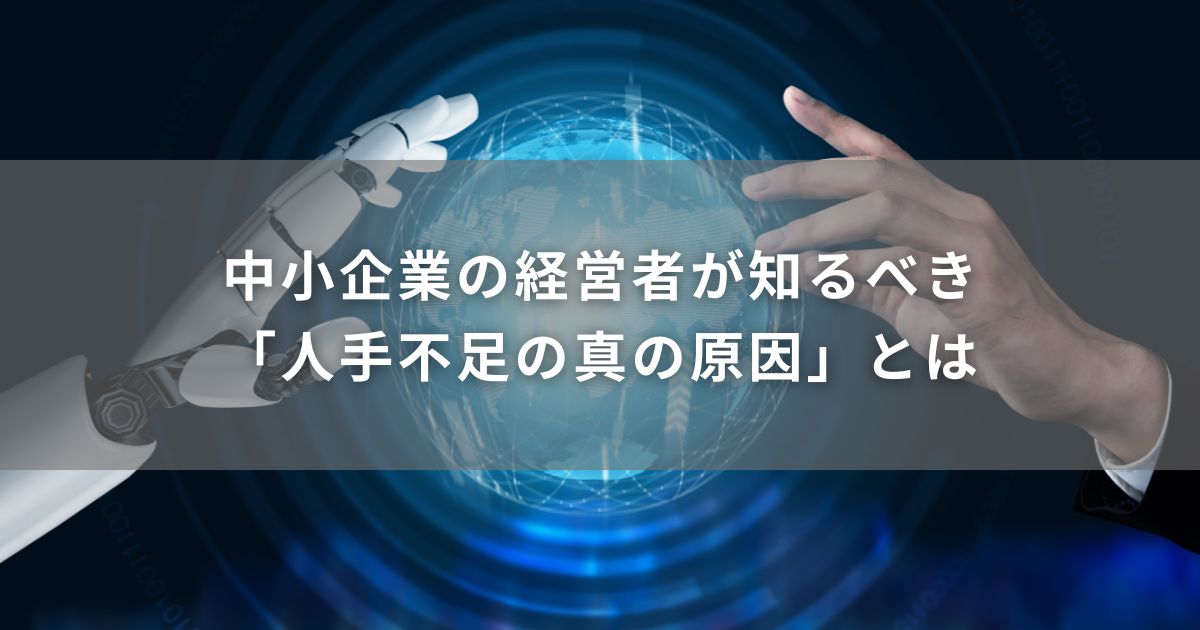
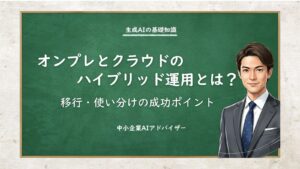
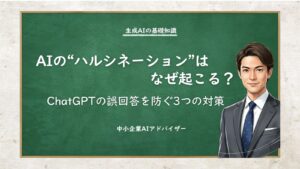
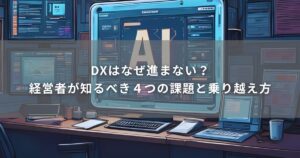


コメント