今、注目が集まっている「Helpfeel」。社内外の問い合わせ対応を効率化できる!と言われていますが、具体的にはどんなことができるサービスなのかご存知でしょうか?
この記事では、Helpfeelの気になるサービス内容について、2025年9月の最新情報を基に導入を検討している中小企業の経営者がよく分かるようにご紹介いたします。
また、数多くの中小企業を支援してきた経験から、どんな企業にマッチするのか、どのような導入メリットがあるのかについて詳しく解説していきます!
この記事にある用語解説
- FAQ(Frequently Asked Questions):よくある質問のまとめ(Q&A集)
- VOC(Voice of Customer):「顧客の声」の略。お客様からの質問や意見、要望をまとめたもの。
- SaaS(Software as a Service):インターネットで使うソフトサービス(月額課金が多い)
公式サイトはこちらから

Helpfeelとは?
「Helpfeel」はFAQ市場においてシェア成長率No.1のFAQシステムです。
顧客向けのFAQと社内向けのFAQの両方に対応しています。
顧客向けのFAQ(カスタマーサポート)では顧客からの電話やメールでの問い合わせを削減し、顧客体験(CX)と満足度を向上します。
社内向けのFAQでは情報システム、人事、総務などへの社内からの問い合わせ対応の負担を軽減し、バックオフィス部門の生産性向上や業務の属人化解消に貢献します。
特許技術でもある「意図予測検索」によって、AIがユーザーの「訊きたいこと」を予測し、最適な回答へと導くことができる技術が、大きな特徴です。
導入の際にも、専属のプロフェッショナルチームによる手厚いサポート体制が用意されており、FAQシステムの新規構築や既存システムからの乗り換えも安心して行えます。
従来のFAQシステムの3つの課題
Helpfeelの性能を見ていく前に従来のFAQシステムが持つ3つの課題を見ていきましょう。
現在、FAQシステムを導入している企業にとっては常に頭を悩ませてきた課題であると思います。
1.ユーザーが求めている回答を見つけられない
従来のFAQシステムの多くは、単純なキーワード検索に依存しています。
そのため、ユーザーが使う言葉とFAQに登録されている言葉が少しでも異なると回答にたどり着けません。例えば、ユーザーが「ログインできない」「ログインできません」のように異なる言い回しを使ったり、漢字とひらがなを混ぜて使ったりすると、FAQがヒットしないことがあります。
欲しい情報が見つからないユーザーはFAQサイトを探し回ることになり、「探し疲れ」を感じてしまいます。結果として実に70%のユーザーが答えを見つけれられずにFAQサイトを離脱してしまいます。
2.問い合わせが減らず、サポート部門の負担が続く
ユーザーが自己解決できないため、結局は電話やメールで問い合わせることになります。これによりFAQシステムを導入しているにもかかわらず、以下のような問題が発生します。
問い合わせ対応の負担が軽減されない
FAQが機能しないため、「よくある質問」への対応に多くの時間とコストが割かれ続け、カスタマーサポート部門の省力化が進みません。
業務の属人化
社内ヘルプデスクの場合、FAQで解決できないため、「知っている人に個別で聞かなければ解決できない」という属人的な対応が無くなりません。
3.FAQの運用・管理が煩雑で効果が出にくい
FAQシステムを効果的に運用するためには継続的な改善が必要ですが、従来の方法では多くの工数がかかります。
例えば、検索ヒット率を高めるために、FAQ記事の細かなチューニングやQ&Aのテストに多くの工数が必要になります。また、ユーザーがどのようなキーワードで検索し、なぜ解決できなかったのかを分析するのが難しく、FAQの内容を充実させるための改善ポイントが一目で分かりにくい状態になってしまいます。
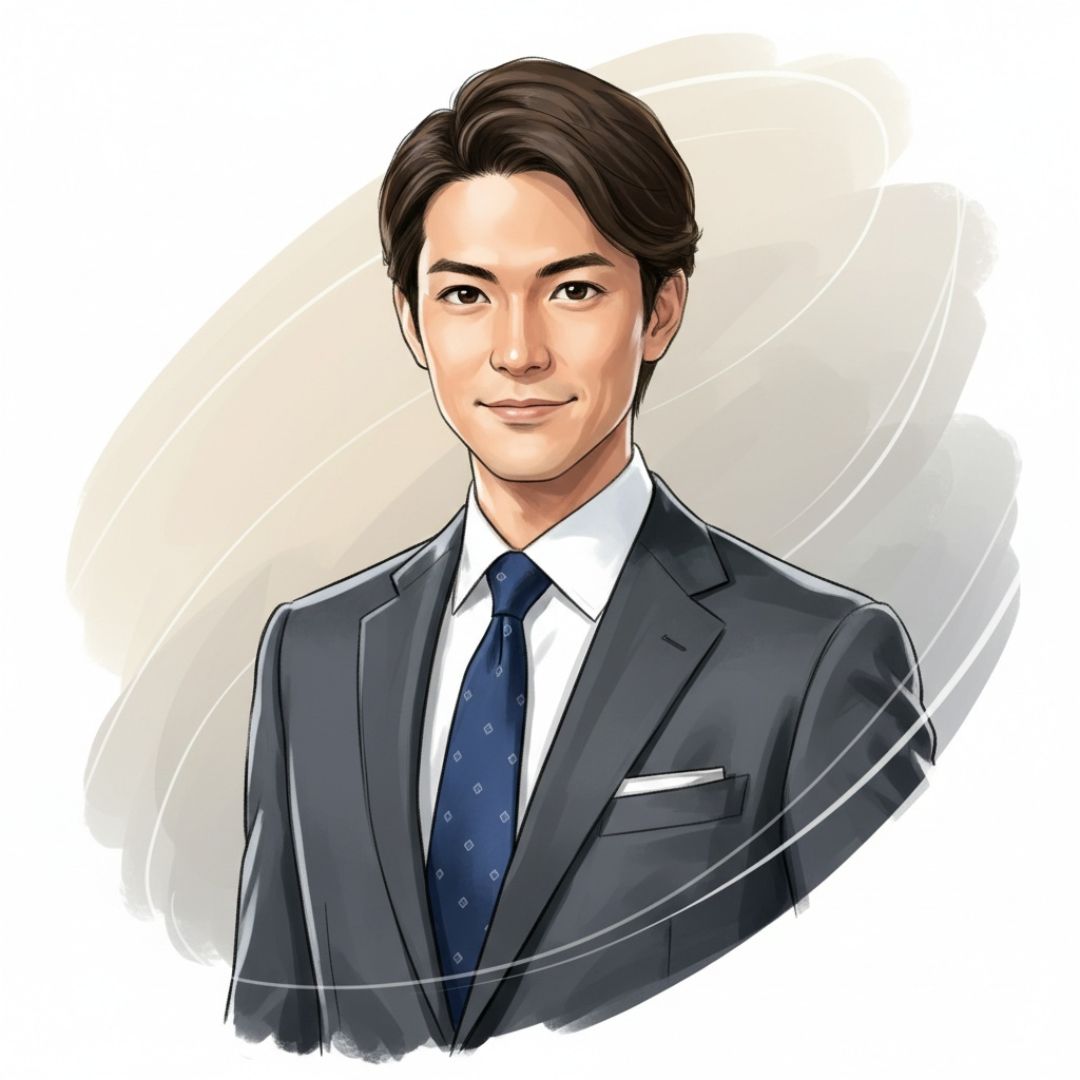
これらの課題を解決するために「Helpfeel」は開発されました。
Helpfeelの基本機能
Helpfeelは初期費用と月額費用の基本料金内で、システムの立ち上げから運用改善までに必要な機能や支援が包括的にパッケージ化されています。
細かいオプションを追加しなくても、問い合わせ削減と自己解決率向上を実現させるための主要な機能を利用できるのが特徴です。
特許技術「意図予測検索」
意図予測検索とは、ユーザーが入力した言葉の「表面」ではなく、その裏にある「意図(本当に知りたいこと)」をAIが推測して検索結果を提示する仕組みです。
この技術のおかげで、表現の揺れや曖昧な言葉にもAIがユーザーの意図を予測して対応し、検索ヒット率98%という高い精度を実現することで、
従来のFAQシステムが抱えていた「答えが見つからない」という根本的な問題を解消しています。
ケタ違いの検索速度
独自開発の検索エンジンにより、約10ms(0.01秒)という高速な検索表示を実現しています。
ユーザーが文字を入力するそばから候補が表示されるため、「入力中に答えが見つかる」というストレスのない検索体験を提供します。
高いセキュリティ
ISMS(情報セキュリティマネジメントシステム)の国際規格「ISO/IEC 27001」を取得しており、万全のセキュリティ体制で情報を保護してくれます。
Helpfeelでできること
【顧客向け】問い合わせ削減と顧客体験(CX)の向上
顧客がFAQサイトで自己解決できるようになり、電話やメールでの問い合わせ件数を大幅に削減します。
24時間いつでも疑問を自己解決できる環境を提供することで、顧客満足度(CSAT)の向上にも繋がります。
さらにFAQの検索ログ(VOC:顧客の声)を分析し、商品やサービスの改善、マーケティング施策に活用できます。
【社内向け】ヘルプデスク業務の効率化
社内規定や業務マニュアルなどを一元管理し、従業員が必要な情報をすぐに見つけられる環境を構築します。
情報システム部門や人事・総務部門への定型的な社内問い合わせを削減 し、担当者の業務負担を軽減します。
これにより、担当者はより重要な戦略的業務に集中することができます。また、専門知識が特定の担当者に集中する「属人化」を解消し、組織全体の知識レベルの底上げをします。
AIを活用した高度な問い合わせ対応と分析
問い合わせ分析(Helpfeel Analytics)
膨大な問い合わせログをAIが自動で分析・分類し、FAQに不足している記事や改善すべき点を可視化します。
チャット形式のUI(Helpfeel Agent Mode)
対話形式で質問に答え、自己解決を促進します。シナリオ設計は不要で、FAQと同じ管理画面で運用できます。
問い合わせ管理(Helpfeel Support)
FAQで解決しなかった問い合わせをAIが自動でチケット化し、分類、担当者割り当て、返信案生成までサポートしてくれます。
Helpfeelの5つの特徴
1.圧倒的な検索技術(技術力)
特許技術「意図予測検索」による高い検索精度と、 ミリ秒単位の高速表示を両立しています。
これにより、ユーザーが「答えを見つけられない」ストレスから解放され、高い自己解決率を実現します。
この検索体験そのものが最大の差別化要因です。
2.手厚い伴走サポート(運用支援力)
ツールを提供するだけでなく、専任のカスタマーサクセスチーム が導入から運用までを徹底的にサポートします。
具体的には、初期のFAQサイト構築、コンテンツ移行支援、月次のデータ分析レポートと改善提案などを基本料金内で行い、専門知識がない担当者でも安心して成果を出せる体制が整っています。
3.柔軟で使いやすいUI/UX(対応力)
シンプルなFAQページだけでなく、ポップアップ表示や 問い合わせフォームへの埋め込み、チャットボット風UI(Agent Mode)使いやすい編集画面により、誰でも簡単に記事の作成や更新が可能です。
4.導入・運用工数の削減(効率性)
AIによる記事ドラフト作成機能 や、プロフェッショナルによるコンテンツ移行・構築サポート により、導入時の負担が大幅に軽減されます。
運用開始後も、Helpfeel Analytics で改善点をAIが特定してくれるため、継続的な改善サイクルを少ない工数で回すことが可能です。
5.データ活用による事業貢献(付加価値)
単なるコスト削減ツールに留まらず、FAQに集まる 顧客の声(VOC)を分析・可視化 し、事業改善に繋げるプラットフォームとして機能します。
検索データをマーケティングや商品開発に活かし、売上向上に貢献します。
Helpfeelを導入するべき企業とは?
Helpfeelを導入するべき企業の特徴について、抱えている課題やこのサービスを導入することで得られるメリットについて詳細に解説します。
自社の現状と比較しながら、サービスの必要性について検討してみてください。
特徴① 問い合わせ量が多く、サポート負荷が常に高い企業
経営課題
- 問い合わせ窓口(電話・メール・チャットなど)がひっきりなしで、対応スタッフが常に手一杯
- 繰り返し似たような質問が来るため、ベテラン社員に依存しており新人育成が追いつかない
- 多くの問い合わせに対して、即時対応できず待たせてしまう、対応品質のばらつきが出る
- 対応コスト(人件費・時間コスト)が売上比でだんだん重くなる
Helpfeelが提供するメリット
自己解決率を高めて問い合わせを減らす
ユーザーがHelpfeel上で疑問を検索すると、そのままFAQ記事で解決できるケースが増えるため、サポート対応を要する問い合わせ件数そのものを削減できます。
対応スタッフの余裕確保
問い合わせが減ると、残った問い合わせ対応に集中できる、品質向上や、不慣れな案件に丁寧に対応できるようになります。
応答速度・ヒット率の改善
Helpfeelは「意図予測検索」により、あいまいな表現・誤字・言い換えにも対応し、ノーヒットを減らす設計になっているため、ユーザーが答えに到達しすくなります。
コスト削減
問い合わせ対応にかかる時間・人件費を抑えられるため、長期的には人を大幅に増やさずに拡張可能です。
特徴② 社内業務(総務・人事等)への社内問い合わせが頻発する企業
経営課題
- 社員からの問い合わせ(パスワード再設定、休暇制度、IT設計手順など)が多く、社内部門が応答に追われて本業やプロジェクト業務が停滞
- ナレッジが属人化しており、担当者しか答えられない「ブラックボックス」が多数
- 社員が情報を探そうとしても見つからず、直接聞きに来る(非効率)
- 新入社員や異動者のオンボーディングが難しく、教育コストがかかる
Helpfeelが提供するメリット
社内FAQとして機能
社内FAQやヘルプデスク用途で、社員が自ら情報を検索し答えを得られるようになる。これにより人事・総務・ITなどの問い合わせ負担が軽減します。
属人化の解消
知識をFAQ記事として定型化・公開することで、誰でも同じように参照できる構造化された知識ベースを作ることができます。
オンボーディングの促進
新入社員や異動者がまずFAQを検索して自己解決できるようになるため、繰り返し聞きに来る時間を減らせます。
ナレッジ更新・改善サイクル
検索ログや未解決キーワードなどを分析し、足りないFAQを補充・改善するサイクルを回しやすくなります。
特徴③ 顧客・ユーザーの声をビジネスに活かしたい企業
経営課題
- 顧客が何を求め、どこでつまづいているのかが「点」でしか把握できず、製品改良・サービス改良に反映できない
- アンケートやヒアリングの反応率・回答の質が低く、顧客の本音を得づらい
- 顧客の課題を予測できないままサービス開発しており、外れプロダクトを作るリスクがある
Helpfeelが提供するメリット
検索ログを”顧客の本音”として可視化
ユーザーがFAQでどのようなキーワードを入力したか、再検索したか、どの回答にたどり着いたかなどの行動ログが取得できます。
これが顧客の「知りたかったこと・困っていたこと」として利用できるようになります。
VOC分析による改善ポイント抽出
未解決ワードやよく検索されるワードをレポート化し、サービス改善案(FAQ追加やUI改善、商品の修正)を提示できるようになります。
問い合わせの内容の予兆把握
FAQの検索傾向をモニタリングすることで、次に来る問い合わせ内容を先読みでき、事前準備や先回り対応が可能になります。
マーケティング/商品企画へのフィードバック
FAQ検索から得られたインサイトを、製品開発・UX改善・販促メッセージ設計などに活かすことで、より顧客視点の改善ができます。
特徴④ 人手不足・コスト制約が強い企業
経営課題
- 顧客数や問い合わせ数が増えているにもかかわらず、対応要員を増やす余裕がない
- 応答遅延や放置・未対応のクレームリスクが高まり、顧客満足度が低下
- コストをかけずにサポート品質を維持・向上させたいが、手段がない
Helpfeelが提供できるメリット
少ない人手でも対応量をカバー
FAQで自己解決できる範囲を広げれば、少人数でも大量の問い合わせを捌きやすくなります。
24時間対応を補完可能
営業時間外や深夜、休日でもFAQが機能していれば、一部ユーザーは自己解決できるため、完全無人対応ではないにせよ応答ギャップを埋められます。
効率化によるコスト削減
問い合わせ対応に割く時間を減らすことで、人件費や残業費用などを抑制できます。
段階的スケール対応
サービス成長に伴って人を大幅に増やす必要なく、FAQベースを拡充して対応力を段階的に強化できます。
特徴⑤ DX・AI活用を模索しているが内部資源が不足している企業
経営課題
- DXを進めたいが、社内にAIやデータ分析に詳しい人材がいない
- AI導入=膨大な初期開発やコストを想像して尻込みしている
- 導入後の運用や改善ができるか不安
- 信頼性・情報漏洩リスクを恐れてAI活用に踏み切れない
Helpfeelが提供できるメリット
ノンエンジニアでも使えるSaaS型導入
クラウド型で、専門知識なしでも運用開始できる設計(FAQ記事を整備するだけで動き始める)
AI活用を段階導入できる
最初はFAQ検索強化だけから始め、次に生成AIによるFAQ自動化、さらにVOC分析活用などステップを踏んでDXを拡張できます。
ハルシネーション対策されたAI設計
AIが誤った回答を出すリスク(ハルシネーション)を抑える設計が施されており、特に正確性が求められる業界でも安心できる仕様です。
伴走支援・改善提案付き
導入後、専任担当者がログ分析・改善施策を提案し、運用の成功を支えてくれます(実施に継続率99%という実績もあり)。
Helpfeelを使う3つのデメリット
1.導入・運用に一定の工数がかかる
Helpfeelは魔法のように全ての質問に自動回答してくれるわけではありません。
まずは土台となるFAQ記事を作る必要があります。
これまでFAQを整備していない企業では、よくある質問を洗い出し、回答文を用意する作業が必須です。
また、導入後もFAQの継続的な更新が欠かせません。
サービス内容の変更や新しい問い合わせが出てきた時に更新を怠ると、古い情報が残り誤った案内につながります。
Helpfeelのカスタマーサクセスチームによる支援はありますが、最終的には企業側が主体となって改善サイクル(PDCA)を回すことが前提です。
2.AIの挙動が分かりにくい場合がある
Helpfeelの強みである「意図予測検索」は、AIが入力内容の裏にある意図を推測する仕組みです。
ただし、従来の単純なキーワード検索とは違い、なぜそのFAQがヒットしたのか直感的に理解しにくいケースがあります。
また、生成AIを活用した回答機能も万能ではなく、ごく稀に曖昧な表現や事実と異なる記述が出るリスクがあります。
特に金融・医療・行政など、回答の正確性が絶対に求められる業界では、導入時や運用時に慎重な検証が必要です。
3.利用されなければ効果が出ない
どんなに優れたFAQシステムを導入しても、顧客や社員が実際に使わなければ意味がありません。
「導入したから安心」と思って周知や運用設計を怠ると、問い合わせ削減などの効果は出ず、投資が無駄になる可能性もあります。
まとめ
この記事では「Helpfeel」のサービス内容や導入するべき企業の特徴について、多くの中小企業を支援してきた経験から解説しました。
ひとつのサービスが社員と顧客の両方にとってメリットを提供できるケースはそう多くありません。
AIを活用した業務効率化の第一歩として、興味のある方はぜひ始めてみましょう。
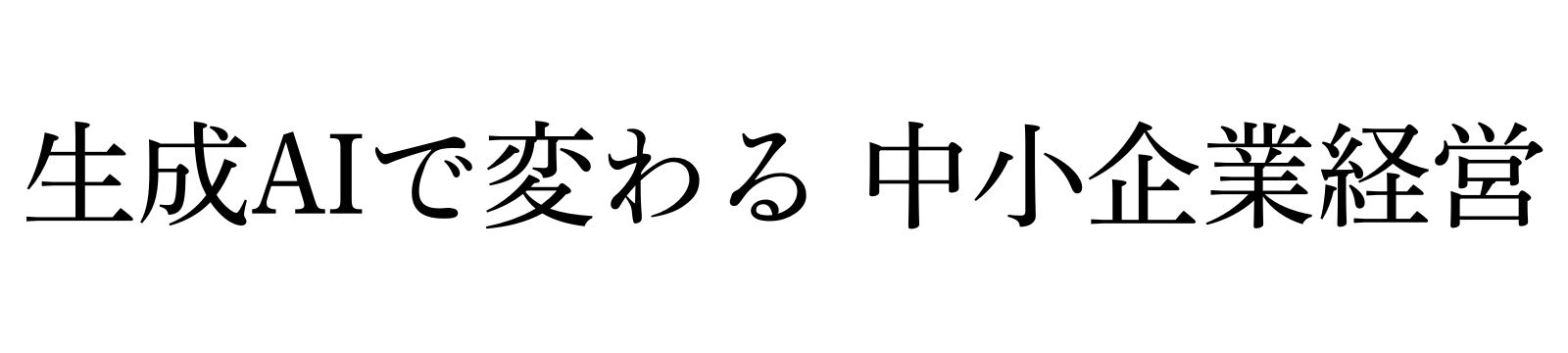

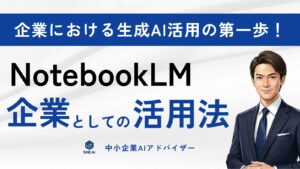

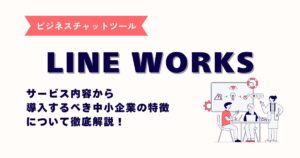
コメント