導入:なぜ日本のAI導入は停滞するのか?

「AI?ウチの仕事は人の勘と経験が命だから」
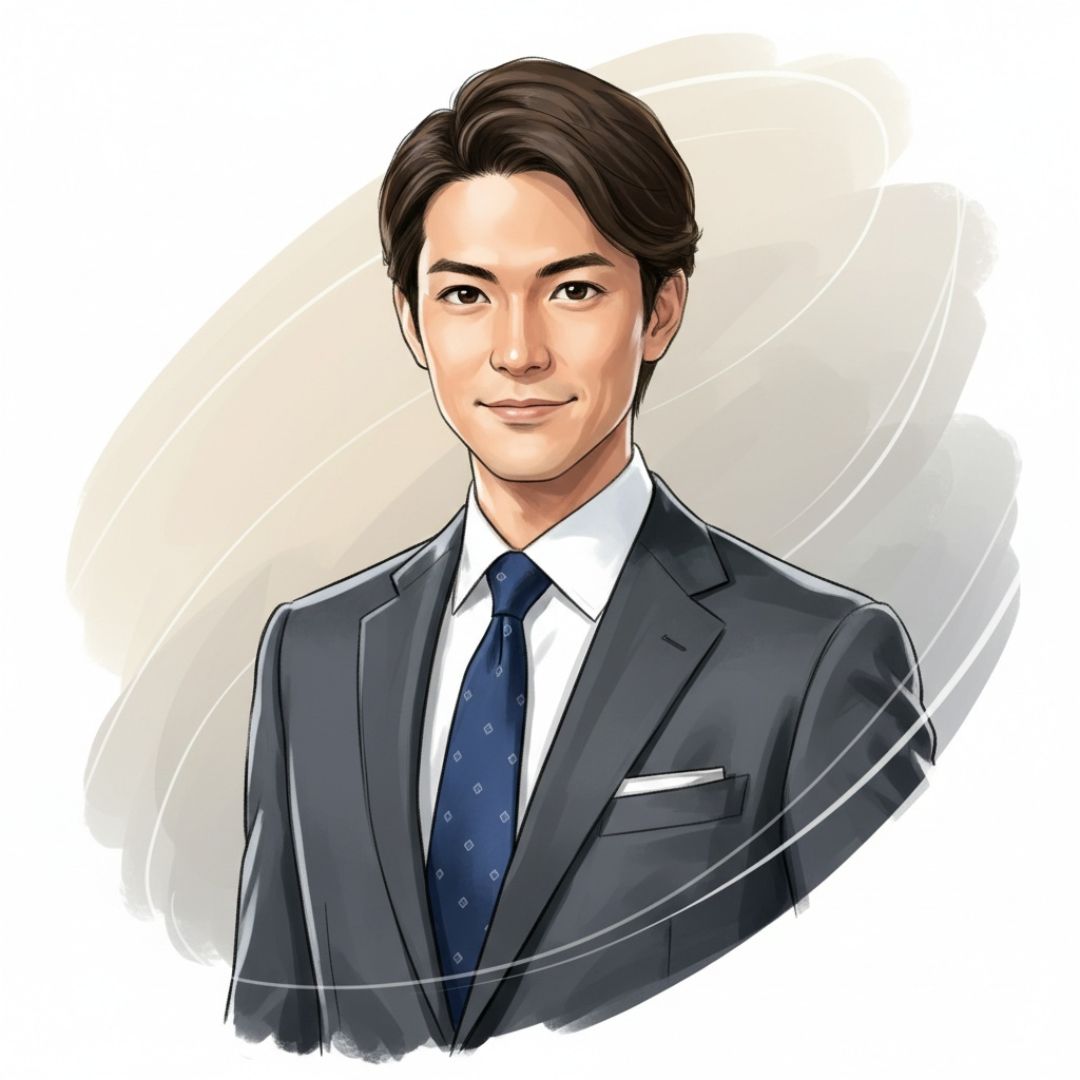
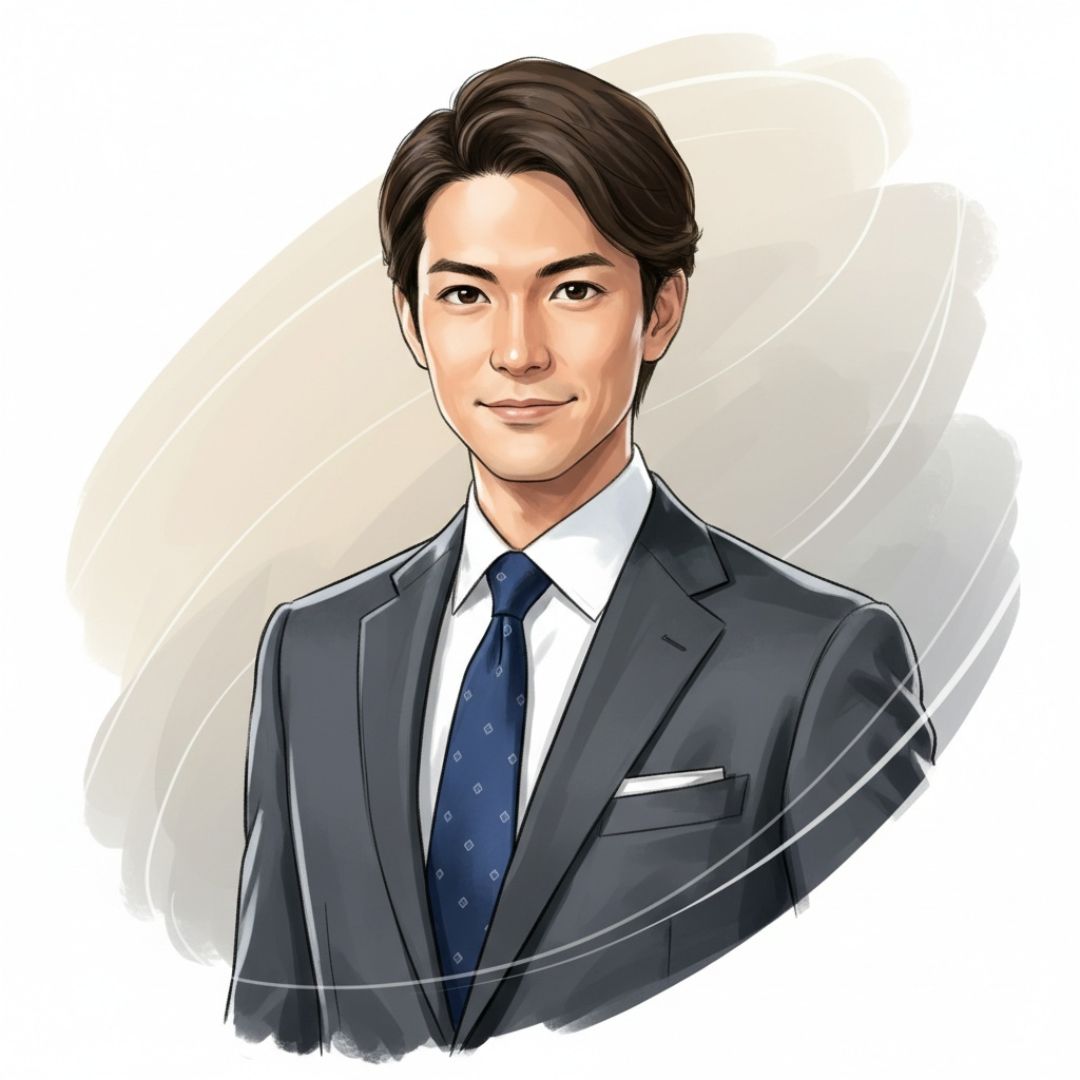
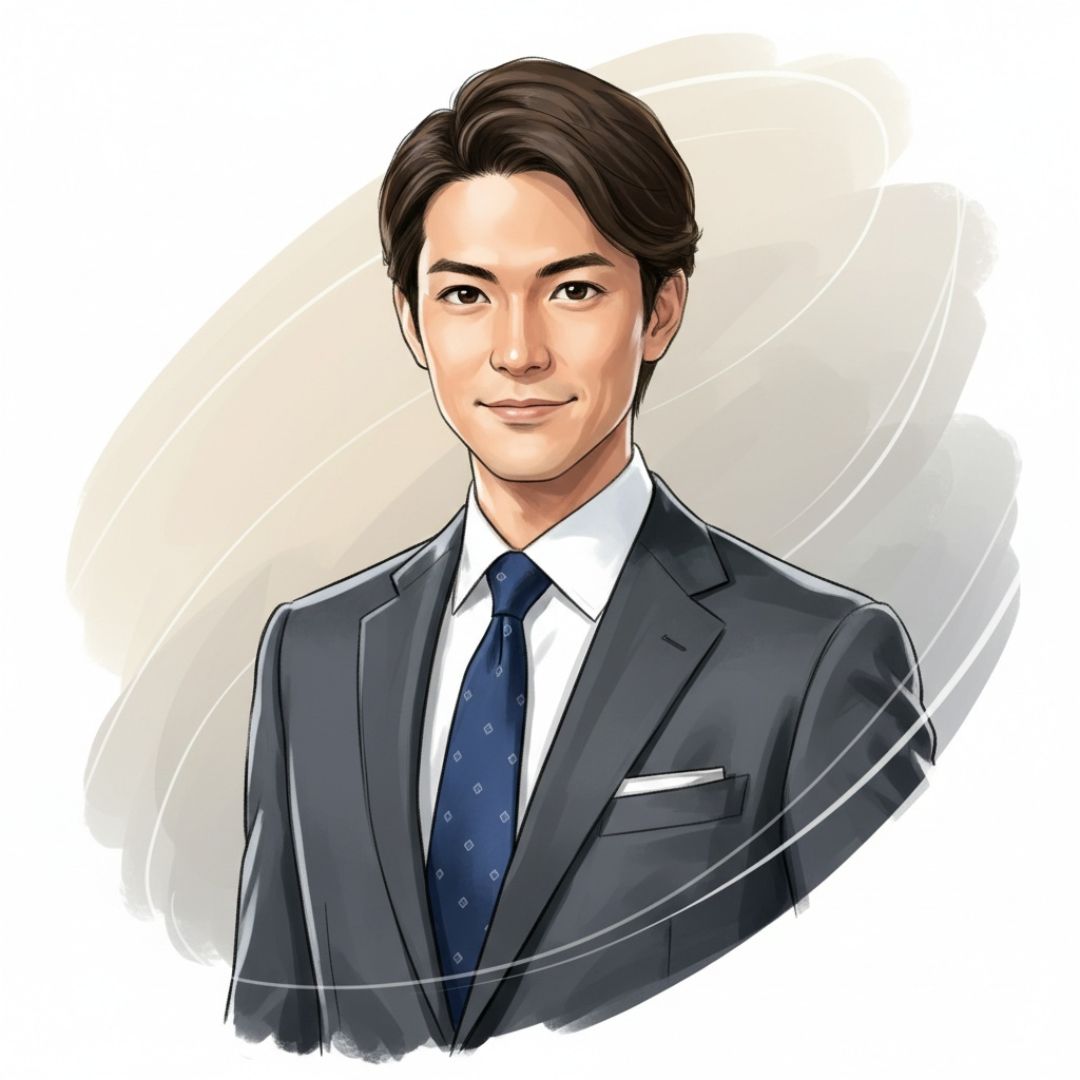
しかし実際には、その”勘と経験”こそAIが最も学習価値の高い資産。職人の技術や長年の営業ノウハウをAIで形式化することで、会社の競争優位を次世代に継承できるのです。
2025年10月現在、日本の中小企業のAI導入率は依然として低水準に留まっています。2024年2月の調査によると、従業員1,000人未満の企業のAI導入率は15.7%程度にとどまっており、従業員10人未満の企業では生成AIの導入率が10%以下と報告されています。一方、従業員10,000人以上の大企業では50%を超える導入率となっており、企業規模による格差が顕著です。
多くの中小企業経営者から聞かれるのは、こうした声です
「AIなんて大企業の話」「うちはそんな最先端なことできない」
「コストがかかりそうで、手が出せない」
「社員にデジタル技術がないから無理」
しかし、数多くの中小企業の経営実態を見てきた経験から言えば、現実にはAIを使い始めた会社とそうでない会社の”差”は確実に広がっています。
特に2024年以降、文章や画像を自動で作れる「生成AI(例:ChatGPT=会話で文章を作るAI、Claude=文書理解が得意なAI、Gemini=GoogleのAI)」が一気に普及しました。これにより、AIの活用ハードルは劇的に下がっています。月額数千円から始められるAIツールが続々と登場し、「大企業の専売特許」という時代は完全に終わりを告げています。
問題は、多くの経営者がAIを「効率化の道具」としか見ていないことです。”効率化止まり”では会社の未来は守れません。なぜなら、効率化だけでは「利益を増やす仕組み」までは生まれないからです。いまやAIを使わないこと自体が、競争上のリスクになりつつあります。
AI活用を「儲け話(戦略ストーリー)」として捉え直す
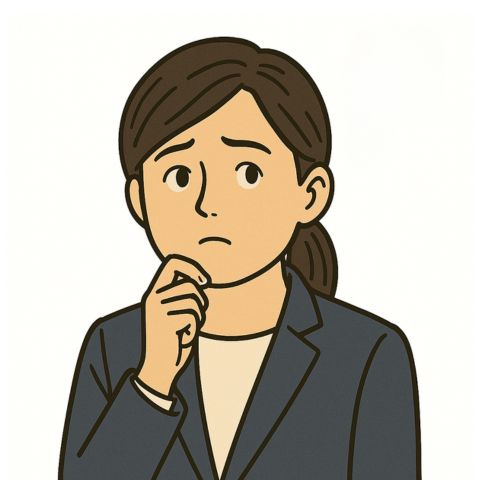
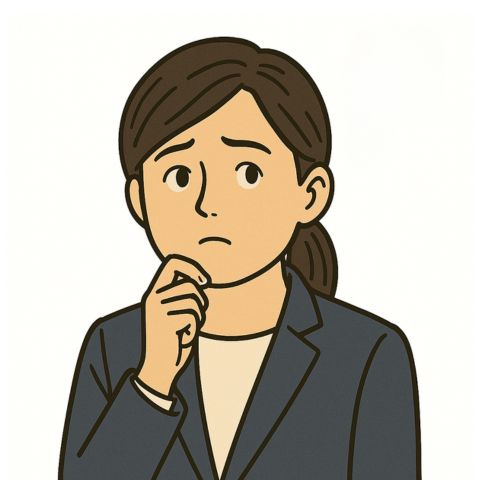
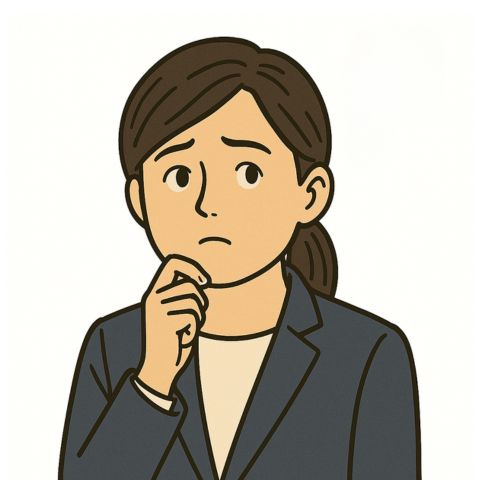
「AIを入れたけど、誰も使っていない」
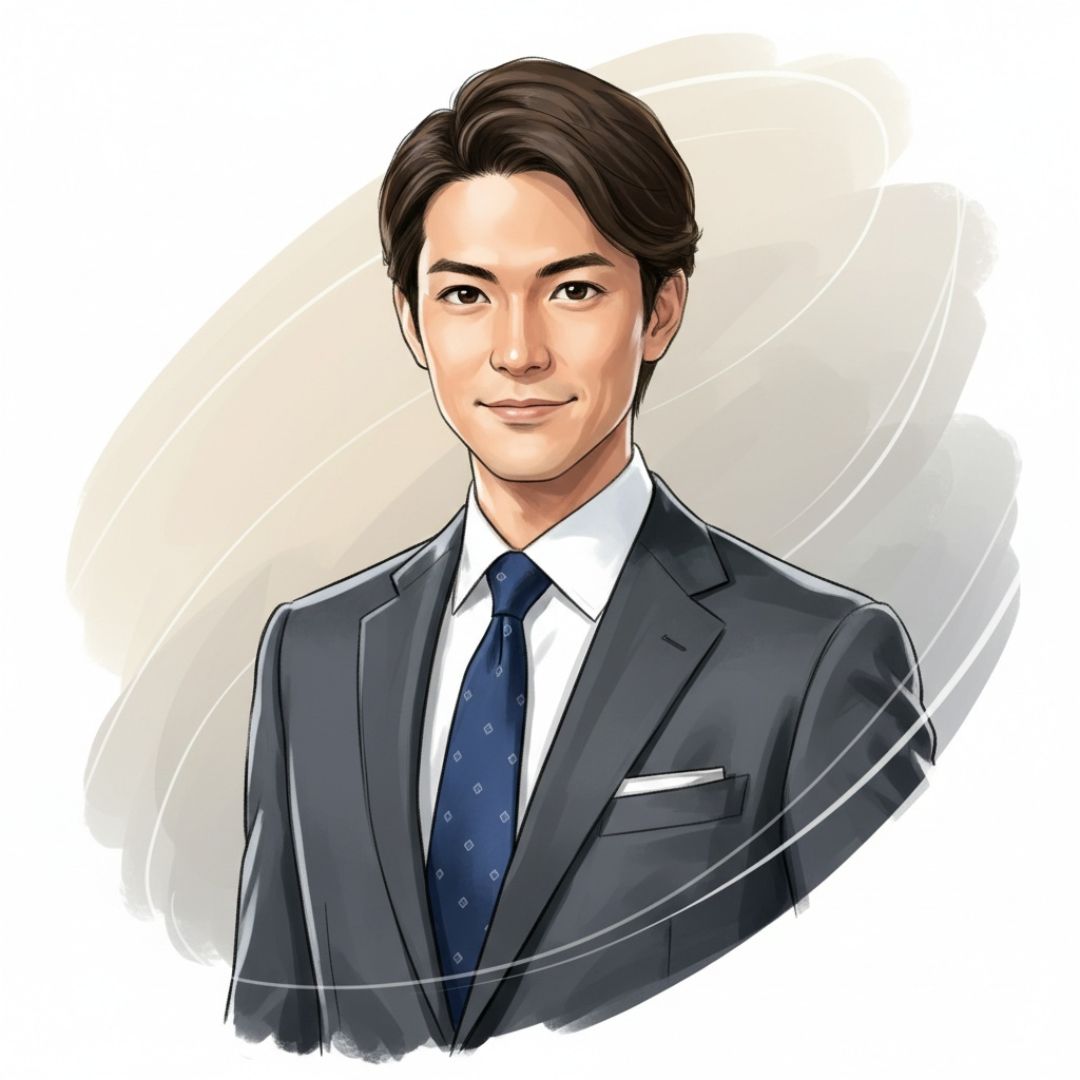
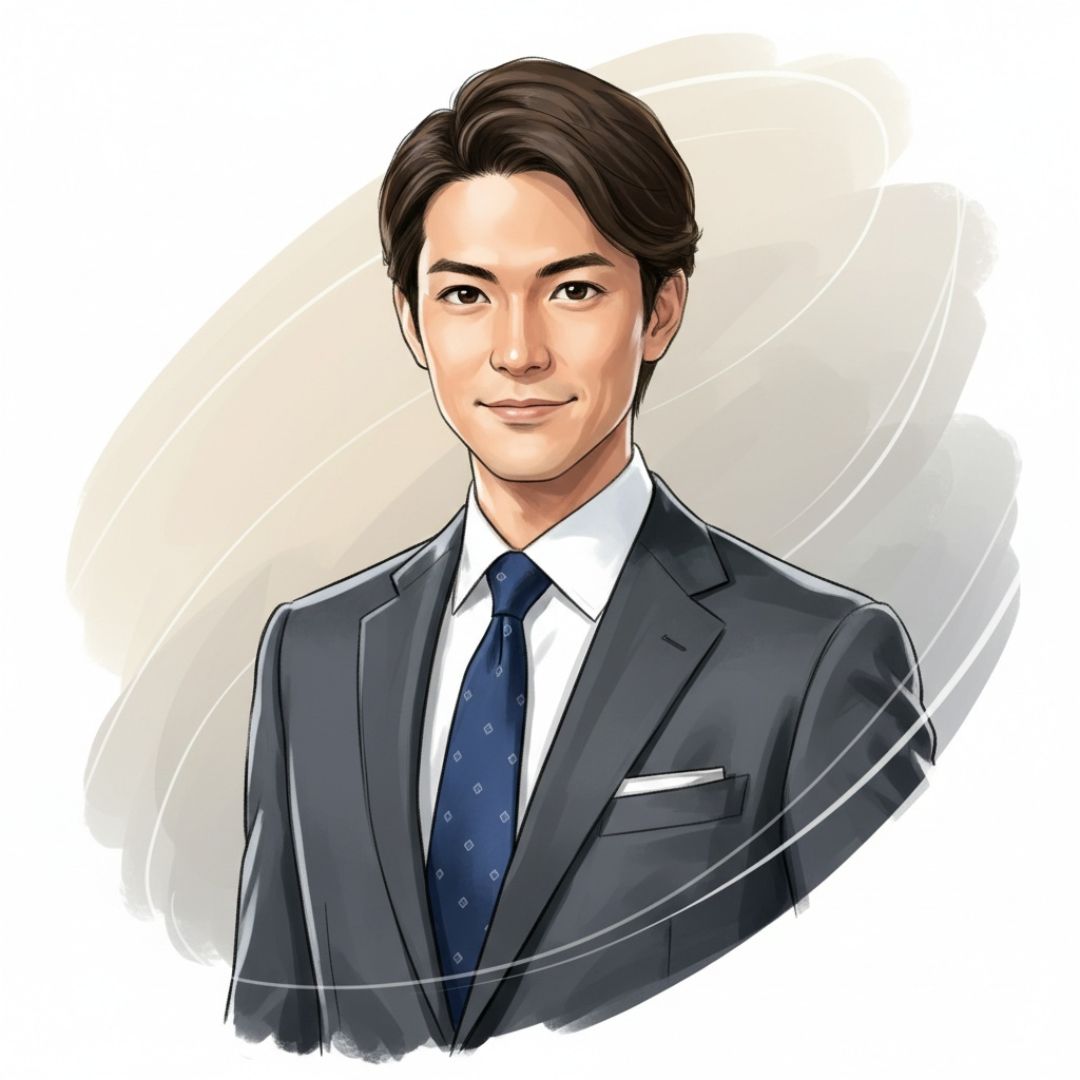
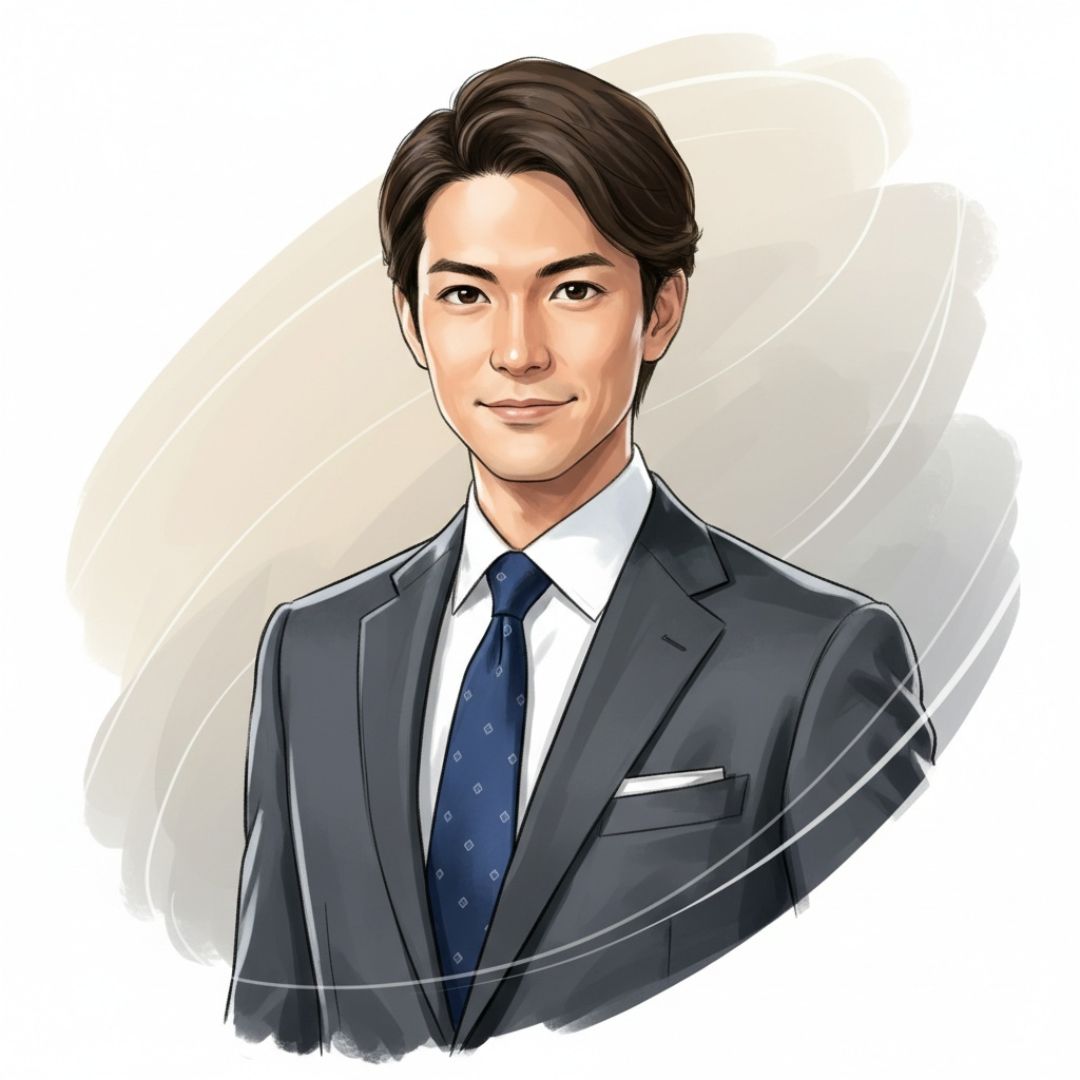
導入の目的が「流行だから」ではなく、「利益ストーリー」に紐づいていないからです。儲け話が明確でないと、社員もAIを使う意味を理解できません。
ここで重要なのは、経営者の本分を思い出すことです。それは「全体の損得構造」を考えることです。
多くの中小企業がAI導入で失敗する理由は、「AI導入」を目的にしてしまうことです。「ChatGPTを導入した」「AIツールを導入した」で満足してしまい、肝心の「なぜそれが必要なのか」が見えていないのです。
正しいアプローチは、AI導入を「コストを下げる」ことではなく、「どうやったらもっと利益を増やせるか」から考えることです。つまり、AI導入は“儲け話(=利益を増やす仕組み)”づくりの一部として捉える必要があります。
戦略が先、AIは後。 AIは”儲け話”を実現するための”道具”にすぎません。会社の活動はすべて因果関係でつながっているため、「AI導入」単体では意味がありません。
例えば、製造業では「AIで品質検査を自動化」する企業が増えています。
しかし大事なのは“自動化”そのものではなく、「不良品を減らしてクレームをゼロにし、その結果リピート客を増やす」といった利益の流れ(儲け話)を設計することです。
飲食店なら「AIで売上データを分析し、次に仕入れるべき食材を自動で提案する」なども同じ考え方です。
「AIで何を自動化するか」ではなく、「AIでどんな利益構造を作るか」を考えることが重要です。
持続的競争優位の源泉:「人」と「AI」の強進化戦略



「あの人しかできない仕事」が多すぎる。
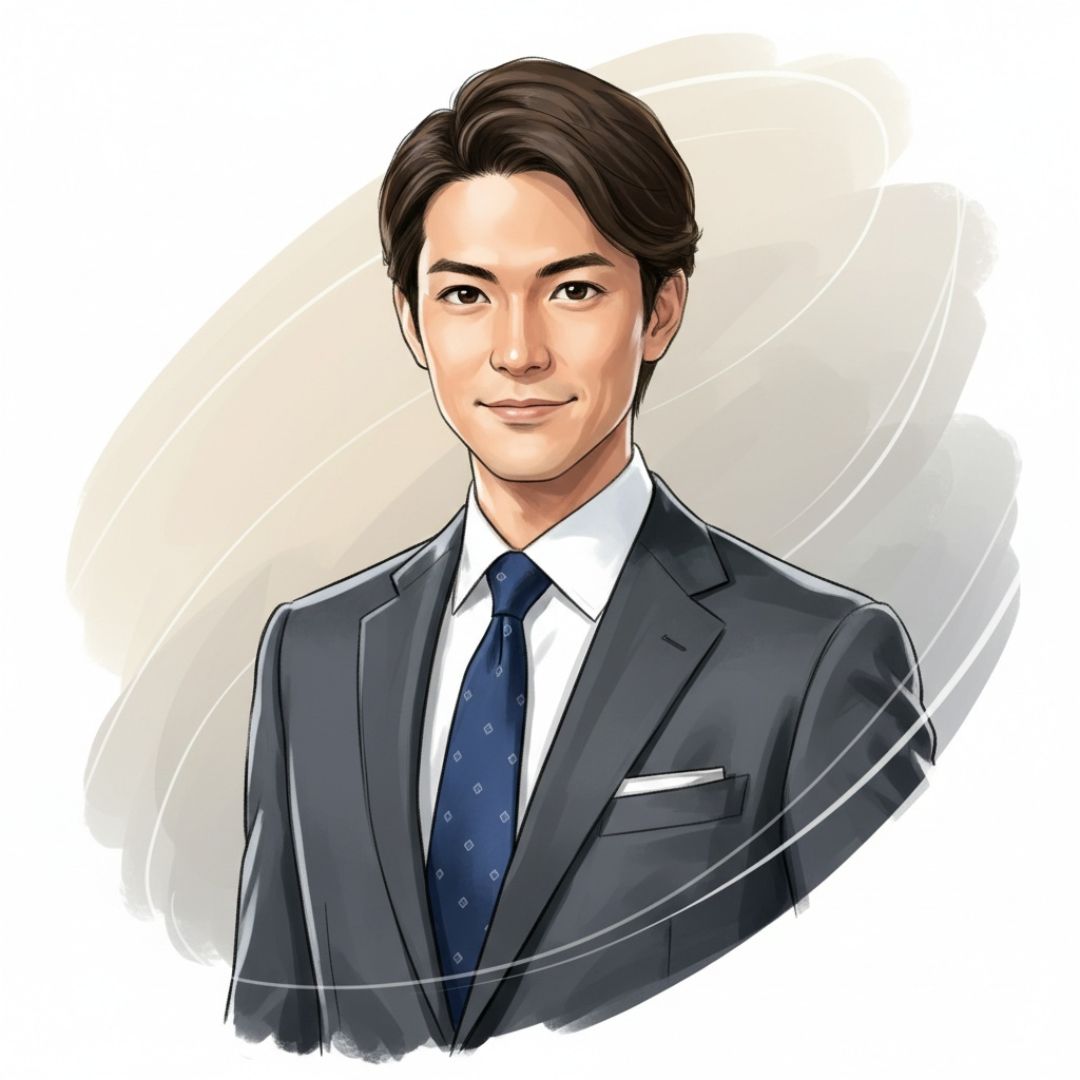
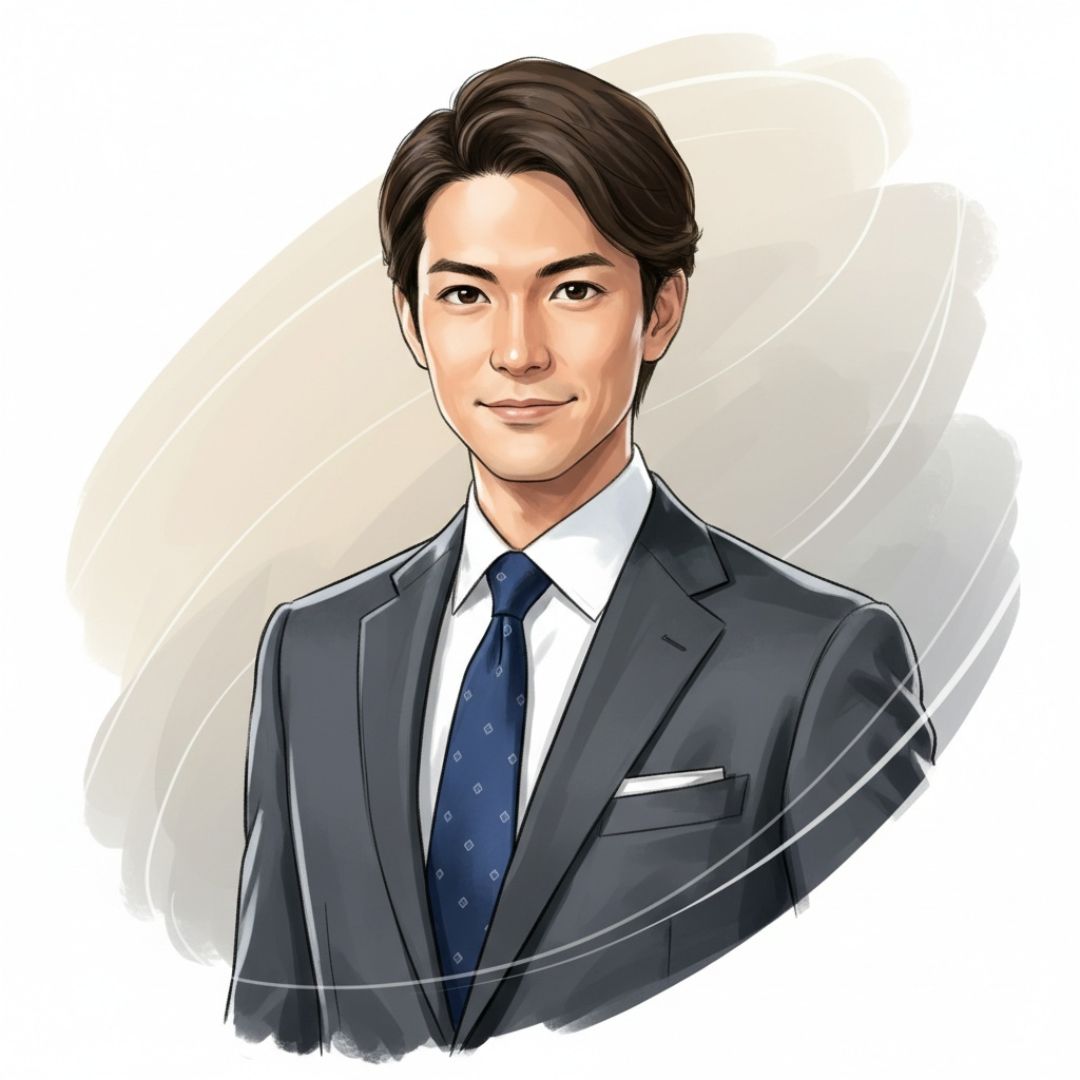
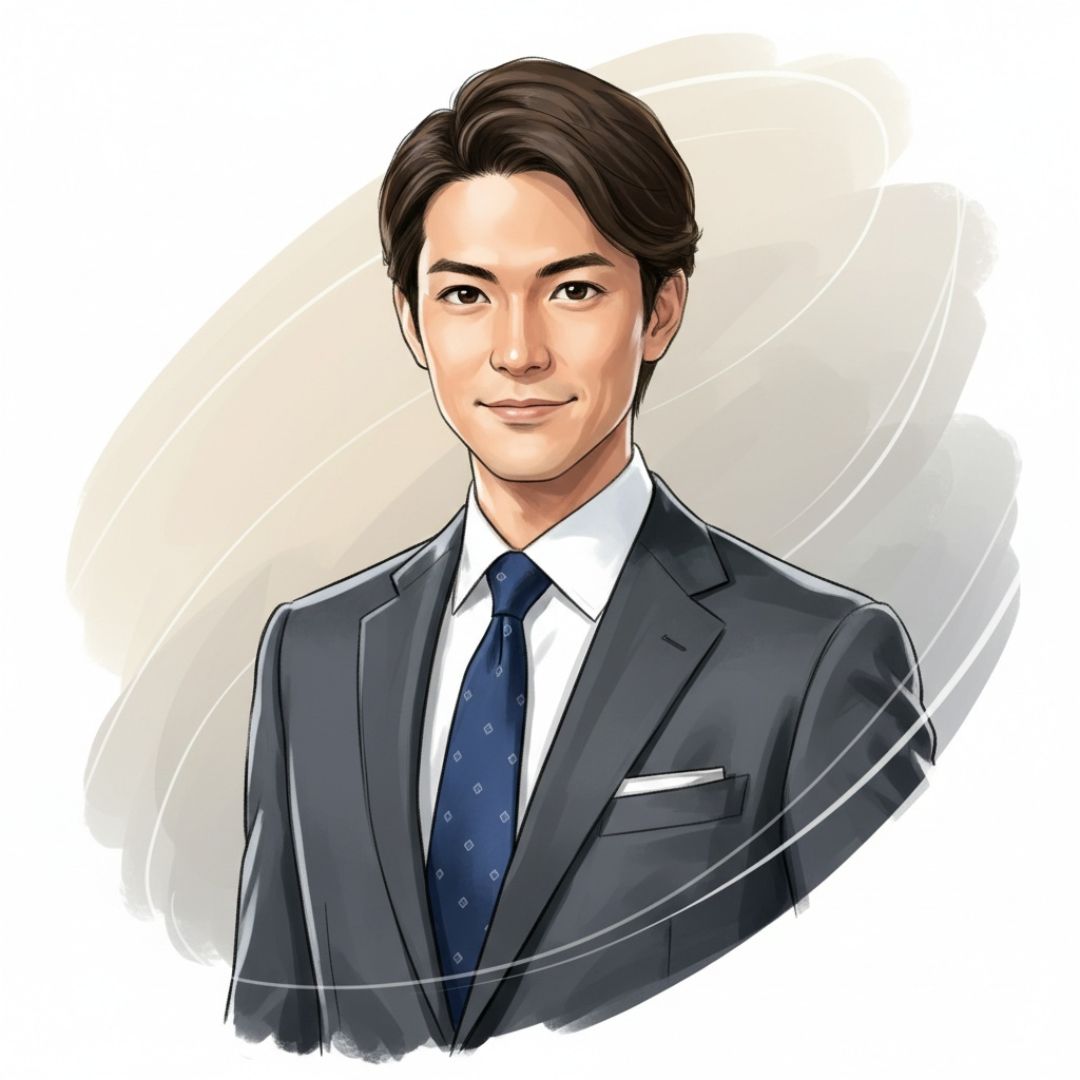
その“属人化”をAIでサポートすれば、仕事のやり方を共有できるようになります。
人が抜けても会社が止まらない仕組みを作ることができます。
2025年の現在、AIは誰でも使える時代になりました。ChatGPTやClaudeのような生成AIは、月額数千円で誰でもアクセス可能です。つまり、AIそのものは差別化要因ではなくなりました。
だからこそ重要なのは、“人との掛け算”です。データや仕組みは真似されますが、人の考え方・文化・関係性は真似できません。
中小企業の最大の資産は、長年培ってきた職人技や顧客との信頼関係といった「暗黙知」です。この「暗黙知」とは、職人の“カン”や“コツ”のことです。
これをAIが「数字やデータとして覚える」ようにすれば、ベテランの技や経験を次の世代に残すことができます。まさに、AIは“知識を引き継ぐ仕組み”になるのです。
「AI × 現場の経験 = 会社のDNAを進化させる仕組み」
つまり、AIは“人の力を奪うもの”ではなく、“人の力を何倍にもする装置”です。
例えば、老舗の和菓子店などでは、職人の「手の感覚」をAIで数値化する取り組みが始まっています。温度、湿度、材料の状態をセンサーで計測し、職人の判断と照合することで、「なぜこのタイミングで作業するのか」という暗黙知をAIが学習し、新人でも職人レベルの品質を再現できるようになる事例があります。
また、建設業では、現場監督の「危険予知能力」をAIで形式化する取り組みが注目されています。過去の事故データと経験豊富な監督の判断基準を組み合わせることで、若手でも高い安全性を確保できる仕組みを構築する企業が増えています。
Ⅳ. 経営者が実践すべき導入アプローチとマインドセット
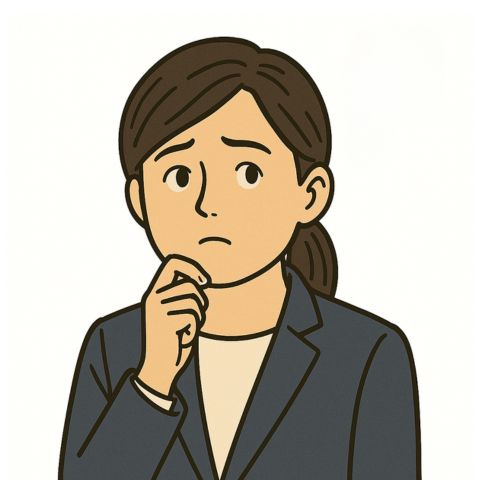
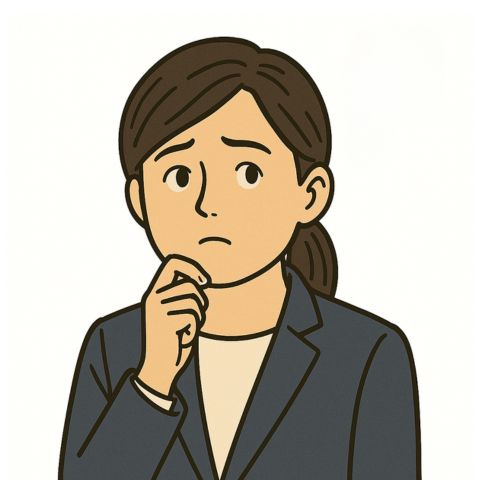
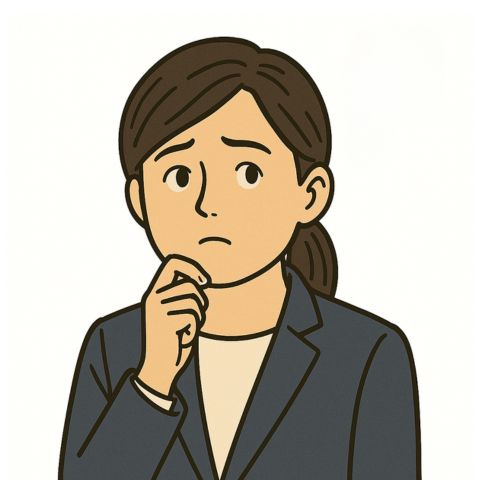
「ウチの社員はデジタル苦手だから…」
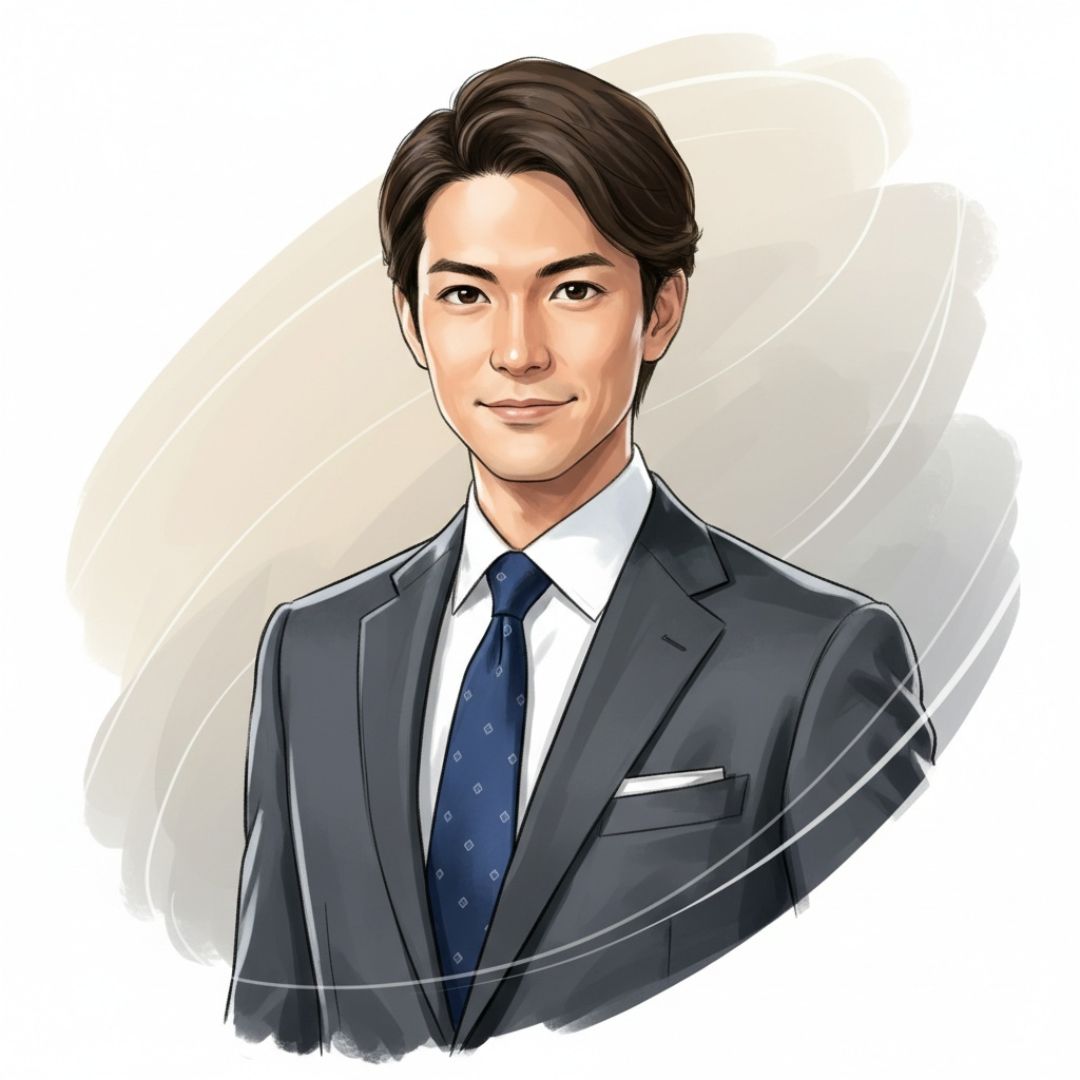
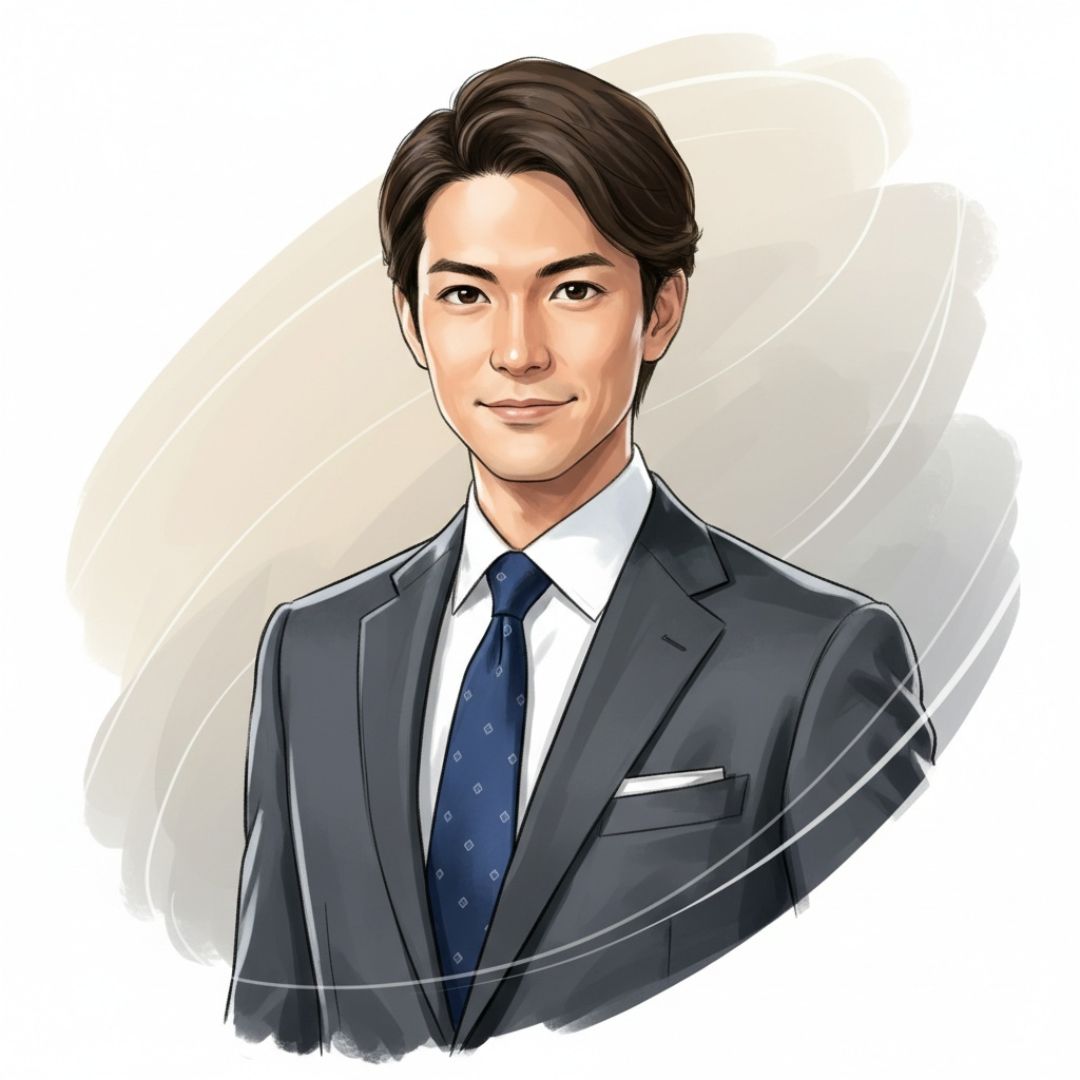
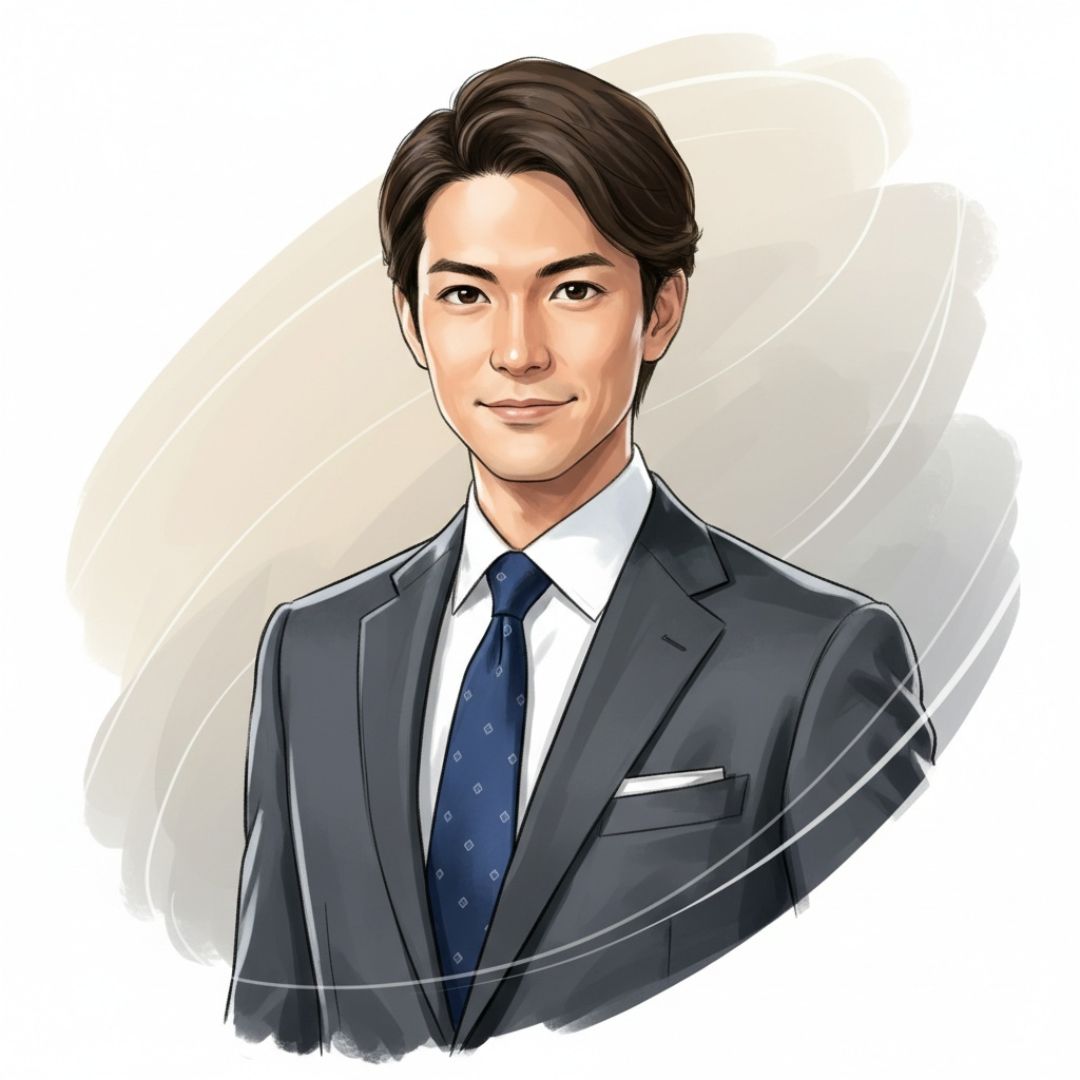
だからこそ”AIがわかる社長”が先に使ってみることが重要。経営者が率先してAIを使い、その効果を示すことで、社員の不安を解消できます。
まず重要なのは、「AIにできるかどうか」ではなく「AIにやらせたらどうなるか」を考えることです。現在の生成AIは、人間が思っている以上に多様な業務に対応できます。
段階的ロードマップ:3段階で無理なく始める
AI導入を3段階で考えることで、ムリなく始められます
レベル1:定型業務の自動化(まずはここから)
請求書作成、FAQ対応、データ入力など、「やることが毎回同じ」仕事から始めましょう。
ChatGPTやNotion AIのようなツールを使えば、月数千円のコストで効果を実感できます。
レベル2:顧客データの分析・売上予測
顧客の購買行動分析、需要予測、在庫最適化など、データを活用した意思決定支援を行います。ここでAIの真価が発揮されます。
レベル3:顧客体験の最適化・新価値創造
AIを活用した新しいサービス開発、パーソナライズされた顧客体験の提供など、競争優位の源泉となる活用です。
データを分断しない仕組みづくり
部署ごとにバラバラなExcelを使っている状態では、AIの力を最大限に発揮できません。
Googleスプレッドシートやkintoneなど、全社で共有できる仕組みを作ることで、AIの精度が格段に上がります。
セキュリティ不安の誤解を解く
「中小企業にはセキュリティが心配」という声をよく聞きますが、現在のクラウドAIサービスは大企業レベルのセキュリティを提供しています。むしろ、中小企業の方が大企業よりも柔軟にセキュリティ対策を導入できる場合もあります。
社員への伝え方
「AIは敵ではなく、仕事を助ける味方」というメッセージを、まず社長自身が発信しましょう。
AIを使うことで社員は単純作業から解放され、もっと価値の高い仕事に集中できます。”AI=人減らし”という誤解を最初に解くのが経営者の役割です。
具体的には
- AI導入により、社員はより創造的で価値の高い仕事に集中できる
- 単調な作業から解放され、顧客との関係構築に時間を使える
- 新しいスキルを身につけることで、キャリアアップにつながる
結論:AIを「儲け話」を実現するための”戦略的インフラ”と捉えよ
2025年10月現在、AIはもはや「便利な効率化ツール」ではありません。
会社の利益の仕組みを作り直す“経営の土台(インフラ)”です。
中小企業にこそ、”AI×人”による新しい商売の物語が必要です。大企業が持つリソースを中小企業が持つことはできません。しかし、中小企業が持つ「現場力」「顧客との距離」「意思決定の速さ」をAIで強化することで、大企業を上回る競争優位を築くことが可能なのです。
重要なのは、「AIで何ができるか」ではなく、「AIでどう儲けるか」を考えることです。
今こそ、経営者自身が「AIで描く儲け話の語り手」になる時代です。
難しい技術の話ではありません。AIをどう使えば自社がもっと儲かるか——その“物語”を描くことが経営者の仕事です。
あなたの会社の「儲け話」は何ですか?その物語を実現するために、AIをどう活用しますか?
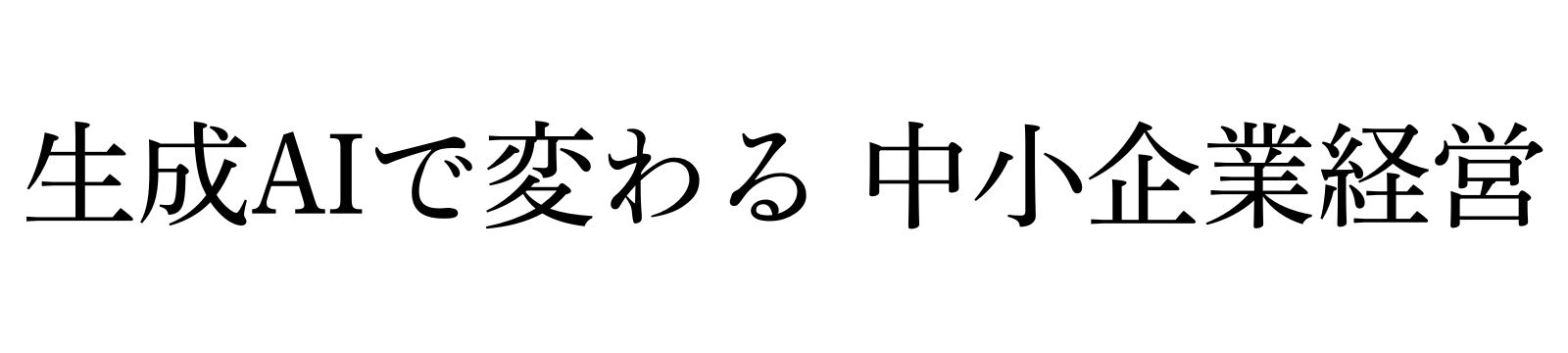
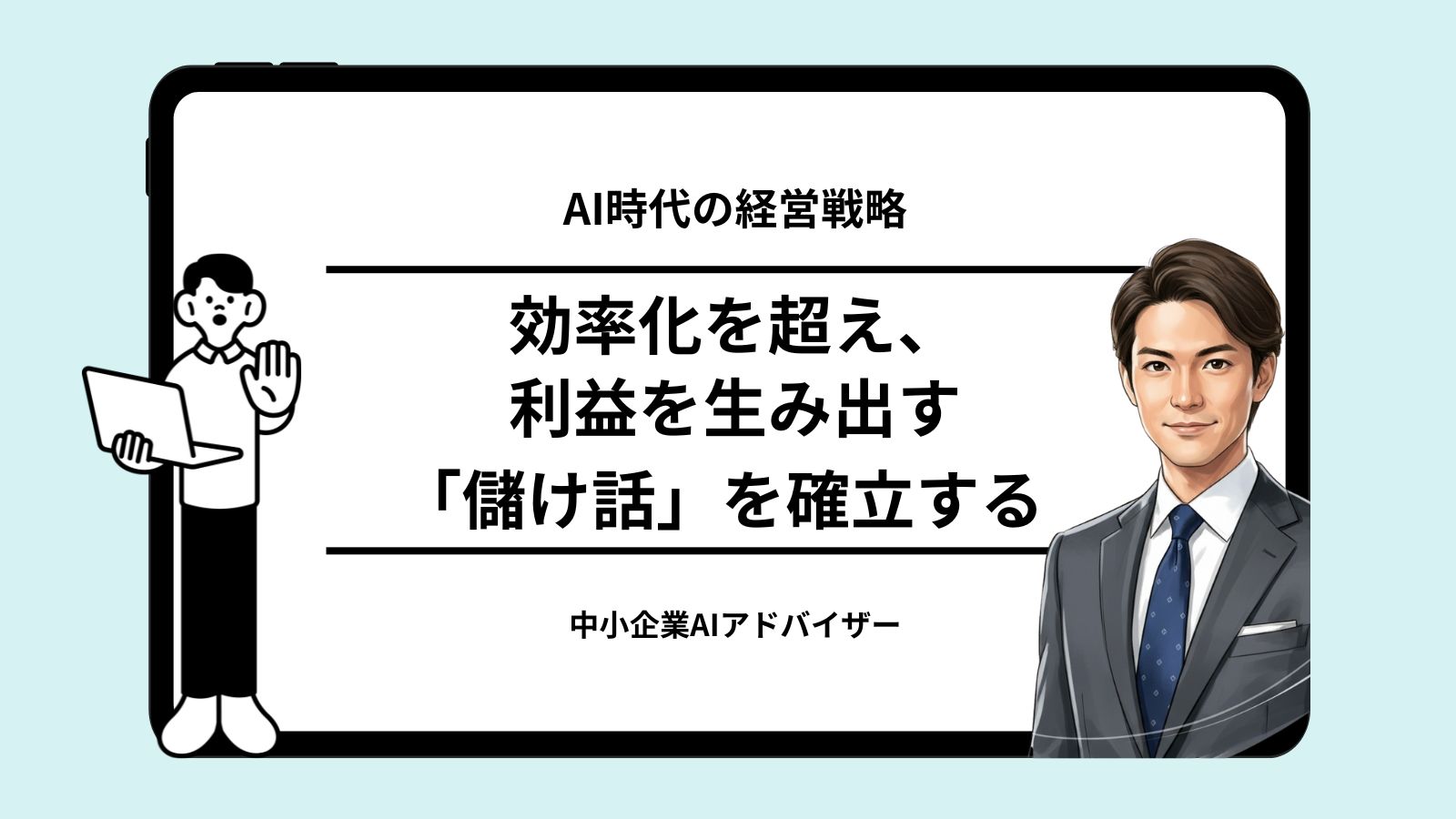
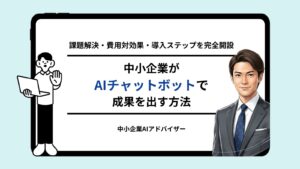
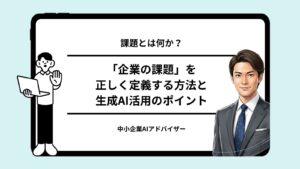
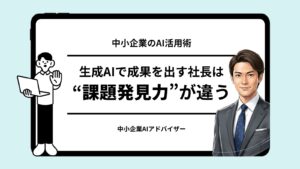
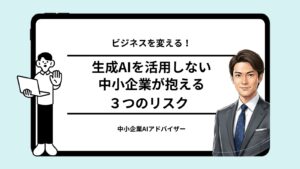
コメント