近年、ChatGPTをはじめとする生成AIが急速に普及しています。しかし、その一方で「ハルシネーション」と呼ばれるAIの誤回答によるトラブルも増えつつあります。
AIを上手に使いこなせる企業とそうでない企業の間には、顧客や社会からの信頼度に差が生まれ始めています。特に情報発信の多い企業では、“AIが作った誤情報”が企業イメージを損なうケースも出始めています。
そのため、「AIは時にもっともらしい嘘をつくことがある」という基本的な理解を持つことが、今や非常に重要となっています。
ハルシネーションとは
ハルシネーションとは、「AIがそれっぽいウソを自信満々に答えてしまう現象」を指します。これは、生成AIが文章を「もっともらしく」作成する仕組みに起因しており、AIに悪意はないものの、重大な誤解につながってしまうことがあります。
たとえば中小企業の実務では、補助金情報や契約書文面、顧客へのメール文案など、身近な場面でもハルシネーションが発生する可能性があるため、注意が必要です。
なぜハルシネーションは起こるのか
生成AIは「意味」ではなく「言葉の並び」を予測している
生成AI(例えばChatGPTなど)は、「意味」を理解して文章を作っているのではありません。AIは、与えられた文章の流れのなかで「このあとに来そうな言葉は何か」を予測し、その確率が高いものを順番に並べて文章を作っています。
たとえば「おはようございます。今日の天気は…」と入力された場合、AIは過去のテキストデータから最も続きやすい表現(「晴れでしょう」など)を選びます。この仕組みによって、AIは一見自然でそれらしい文章を作ることができます。しかし、AI自身はそれが事実かどうかを理解して判断しているわけではありません。
つまり、「もっともらしいこと」を答えることはできますが、内容の真偽までは保証していないのです。
なぜ「知らないこと」にも答えてしまうのか?
生成AIの多くは、質問を受けた際に「わかりません」と正直に答えることはほとんどありません(一部の慎重に設計されたモデルを除きます)。
その理由は、AIの訓練過程にあります。AIは「空白になっている部分をもっともらしく埋める能力」が重視されるように設計されており、何も答えないことは性能が劣ると評価されがちです。そのため、たとえ正しい情報を知らなくても、AIは与えられた質問に対して、できるだけそれらしい回答を作り出そうとする傾向があります。これが、知らないことについても”それっぽい返答”を返してしまう理由です。
学んだのは「知識」ではなく「言語のパターン」
人間は物事の「意味」や「常識」を理解して、文脈や前提を踏まえて判断することができます。一方で、AIは膨大な文章データを学習し、「こういう質問にはこういう答え方が多い」といった言語表現のパターンを身につけているに過ぎません。つまり、AIは百科事典の知識を体系的に暗記しているわけではなく、むしろSNSの投稿を大量に読み、その中から使われやすい言い回しや傾向を掴んでいるようなものです。
この仕組みによって、AIは一見もっともらしい返答を返すことができますが、初めて見る事実や新しい状況に対しては弱く、内容が間違っていたり事実と異なっていても、違和感なくそれっぽい答えを生成してしまうことがあります。
「考えている」わけではなく「確率で埋めている」
生成AIが文章を作る仕組みは、「Aの次にはBが続きやすい」といった統計的なパターンや確率にもとづいています。つまり、与えられた文脈や単語の並びから「もっとも可能性が高い」と判断される語句を選び、文章を組み立てているのです。AIは実際にその内容が正しいかどうか、事実に基づいているかどうかを調べて答えているわけではありません。
たとえば、「火星には海がありますか?」と質問すると、AIは過去のデータやよくあるパターンから「火星にはかつて海があったと考えられています」など、それらしい回答を作り出すことができます。しかし、その内容が現在も真実であるかどうか、あるいは正しい最新情報に基づいているかどうかまではAI自身が判断していません。このように、生成AIは「確率的に自然な文章」を生成できても、「論理的な検証」や「事実確認」を自律的に行っているわけではない点に注意が必要です。
確率的生成の副作用:もっともらしいウソができあがる
LLM(大規模言語モデル)は、「正しい答え」を重視するというよりも、「もっともらしく見える答え」を優先して出力する傾向があります。これにより、表面的には説得力があって立派に見えるものの、内容が誤っていたり、根拠のない情報が含まれてしまう”ハルシネーション”と呼ばれる現象が発生します。特にビジネス文書や専門的な解説風の文章では、あたかも事実であるかのように自信を持って語る「言い切り」のスタイルが多用されるため、利用者は十分に注意する必要があります。
「検索」ではなく「創作」に近い
Google検索が既に存在する情報をインターネット上から探し出すツールであるのに対して、生成AIは過去に学習した知識をもとに新しい文章を「作り出す」存在です。つまり、生成AIは情報の「検索」ではなく「創作」を行っているため、私たちはAIが文章を「探している」のではなく「作っている」という点を理解しておく必要があります。このようにAIが文章を生成する過程では、出典や根拠が明示されていなければ、その内容が正確であるという保証はありません。
例:AIに「2025年の日本の消費税率は?」と聞いてみると…
たとえば、「2025年の日本の消費税率は?」とAIに尋ねた場合、本来の正しい答えは「現時点では消費税率に変更はありません」です。しかし、AIはしばしば「2025年から12%に引き上げられました」といった、もっともらしい誤った情報を自信満々に返すことがあります。これは、AIが過去のデータから「〇年に税率が変更された」という表現パターンを学習しており、そのような返答が”ありそう”な文脈として確率的に導き出されてしまうためです。このように、AIは事実に基づいて回答しているのではなく、「確率的に自然に見える文章」を生成しているだけである、という点に注意が必要です。
ハルシネーションが起こりやすいケース
| 起こりやすい質問タイプ | 例 | なぜ起こるのか |
|---|---|---|
| 最新情報・ニュース | 「2025年の補助金制度は?」 | AIの学習データが古い可能性がある |
| 固有名詞・専門用語 | 「○○社の新商品仕様は?」 | 訓練データに含まれない固有情報 |
| 曖昧・推測を含む質問 | 「たぶん〜ですか?」 | 推測を促すと“もっともらしい嘘”を生成しやすい |
| 誤った前提の質問 | 「A社が倒産した理由は?」(実際は倒産していない) | 前提が誤ってもAIはそのまま話を続ける |
ハルシネーションを含んだ情報を公開した際のリスクと責任
公開媒体別に想定されるリスク
SNS投稿(企業公式・個人アカウント問わず)
- 誤情報の拡散 → 企業・個人の信用失墜、炎上、謝罪・訂正対応
- 虚偽の第三者情報を含んでいた場合:名誉毀損・業務妨害となる可能性(民事責任)
- 商標・著作物の誤引用・誤説明:知的財産権侵害や不正競争防止法違反の恐れ
営業資料・提案書
- 間違ったデータや法律解釈を含んだ資料で契約・取引した場合、損害賠償請求の対象になりうる
- 誤解を与える記述(例:「国の認可済み」など)→ 景品表示法に基づく措置命令の対象
社内報・従業員教育資料
- 内部向けでも、ハルシネーションによる誤った制度解釈・数値・人物評価が含まれた場合、組織運営上の混乱や社員間トラブルに発展する恐れあり
- 特に人事・評価・法務に関する内容は要注意
ハルシネーションを防ぐ・見抜く方法
- 生成AIの回答には「出典確認」を必ずセットにする
→ たとえば「この内容の根拠を示して」とAIに追質問すると、出典の有無を確認できます。 - 社内では「AI文書レビュー担当」を設ける
→ AIで作成した提案書・契約書・広報資料は、必ず人の目で最終確認を行う体制を整えましょう。 - ChatGPTなどの「引用元表示機能」を活用する
→ ChatGPTやGeminiなど、最新モデルには引用元を表示する設定があります。可能な場合はこれをONにし、根拠のある回答のみを採用します。
経営者・担当者が今日からできる3つの行動
- AIの回答を鵜呑みにせず、必ず人が確認する
- 社内のAI利用ルールを明文化し、共有する
- 誤情報発信時の対応フロー(削除・訂正・謝罪)をあらかじめ決めておく
これらを実践することで、生成AIを“信頼を守るためのパートナー”として活用できるようになります。
まとめ:AIを”使いこなす人”になるために
AIはとても便利な道具ですが、必ずしも正しい答えを出すわけではありません。そのため、AIが出した内容をそのまま信じるのではなく、「本当に合っているのか?」と必ず誰かと確認したり、他の方法でも調べてから使うことが大切です。経営者の方は、社員にも「AIの答えは必ず一度確認してから使いましょう」と伝えてください。
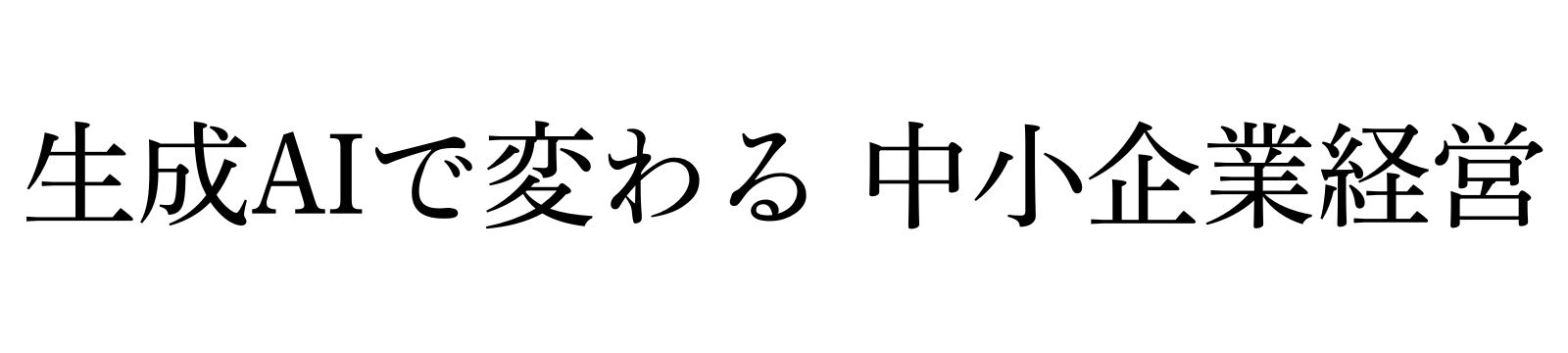
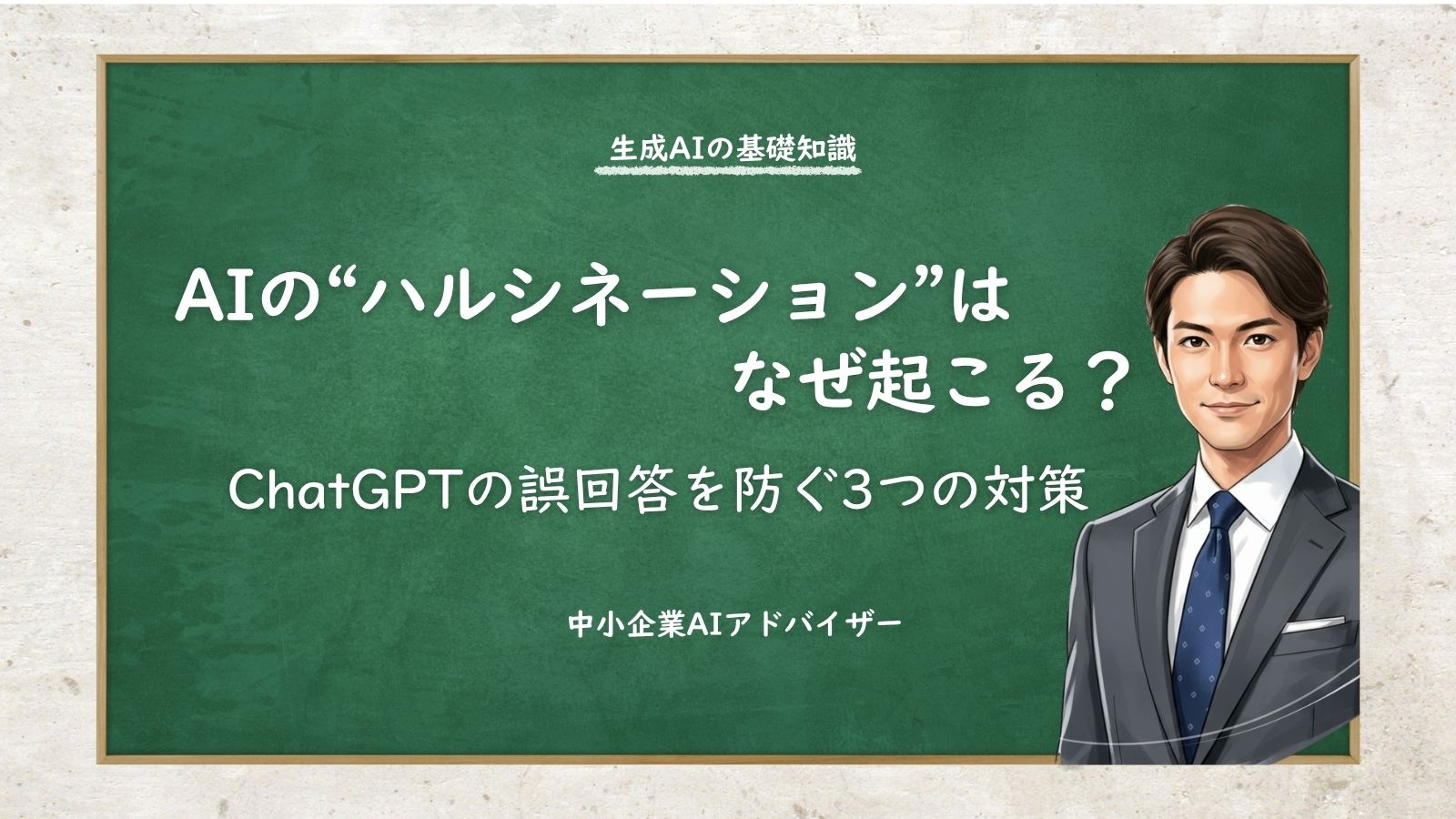
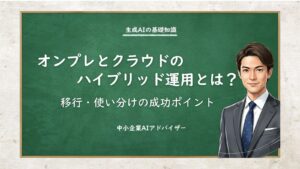
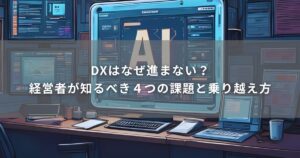



コメント
コメント一覧 (1件)
[…] AIの“ハルシネーション”はなぜ起こる?ChatGPTの誤回答を防ぐ3つの対策 […]